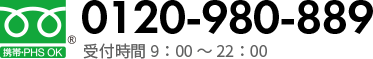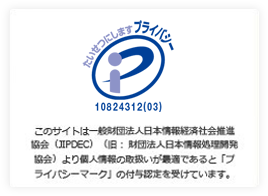発達障害の子どもが不登校になってしまう原因と解決法を紹介!通信制高校なら無理なく進学できる 更新時間 2026.01.08
現在日本では発達障害の子供が10人に1人程度居ると言われたています。
発達障害は見分けがつきにくく、大人になっても理解されないまま放置されていることが多いです。
世間的にも認知度が低く、発達障害の子供が不登校になってしまう事例もあります。
今回は発達障害の子が不登校になってしまう原因と解決方法を紹介します。
不登校になってしまい、進学に困っている保護者は必見です。
発達障害で不登校になってしまった子向けの進学コースも紹介するので参考にしてください。
発達障害が原因で不登校になっている子供へのサポート体制が万全な通信制高校3選
発達障害が原因デフ投稿になっている子供へのサポート体制が万全な通信制高校を3校紹介します。
サポート体制が充実している通信制高校
- 湘南国際アカデミー高等部
- KTCおおぞら高等学院
- 八洲学園高等学校
近年発達障害の認知度が高くなり、サポート体制を強化している通信制高校が多数あります。
これから紹介する通信制高校は、無理なく高卒資格を取得できるプログラムを提供しているのでおすすめです。
各生徒の状況によって柔軟に対応してくれるので、進学について悩んでいる人はしっかりみていきましょう。
湘南国際アカデミー高等部は不登校やひきこもり経験のある人向けのコースを提供
湘南国際アカデミー高等部は、不登校やひきこもり経験がある生徒への支援が充実しています。
通学日数も調節可能で、自分のペースで通学日数を増やしたり減らしたりすることができるのです。
コースを途中で変更することも可能なので、無理に我慢してプログラムをこなす必要はありません。
各生徒の意思を尊重してくれるので、おすすめの通信制高校です。
KTCおおぞら高等学院は高校卒業後の進路までサポートしてくれるから安心
KTCおおぞら高等学院は高校卒業後の進路までしっかりサポートしてくれる通信制高校です。
進路だけでなくメンタル面もサポートしてくれるので、不安や心配事があってもすぐ対処してくれます。
型にはまらない高校生活を送れるので、生徒の個性を上手く活かせます。
勉強以外のユニークレッスンも提供しているので好きなことを伸ばしたい生徒におすすめです。
八洲学園高等学校は発達障害の子供を支援する特別プログラムを提供
八洲学園高等学校は発達障害などでより支援を要する人用のクラスがあります。
5年制になっているので、勉強に追われること無くのびのびと学習することができます。
社会生活を送るための知識もしっかり身につけられるので、生徒の自信に繋がります。
卒業後を見越したカリキュラムになっているので生徒達の特性を把握・理解をしっかりしてくれるので、気軽に相談してみましょう。
その他通信制高校のメリットについて更に詳しく知りたい方は「通信制高校のメリット・デメリットを完全解説!」を読んでみてください!
発達障害の子が不登校に陥る原因
発達障害の子供は、発達障害でない子供より不登校に陥る可能性が高く、2020年現在不登校の7~8割が発達障害の子供と言われています。
発達障害の子供が不登校に陥る原因をまとめました。
発達障害の子供が不登校に陥る原因
- 学校での集団行動に上手く馴染めない
- 親からのプレッシャーで追い詰められる
- 発達障害の理解が無い人たちが周りに居る
学校では集団行動が基本です。
個性を伸ばせるような学校もありますが、強調性を意識した生活を強いられることもあります。
生活環境だけでなく、学習スピードも一貫しているのでついていけない子供は劣等感を感じやすくなるのです。
【原因1】学校での集団行動に上手く馴染めない
学校では集団行動を求められるケースが多く、発達障害の子供にとって厳しい環境になっている場合があります。
更に周囲が発達障害と気付かず、人と違う部分を指摘してしまうので不登校を加速させてしまいがちです。
親側も発達障害と気付かず、知らない間に子供にとって辛い環境を強いているケースもあるので、子供の変化を逃さずしっかり対応する必要があります。
【原因2】親からのプレッシャーで追い詰められる
上記でも軽く説明しましたが、子供が発達障害と気付かず追い詰めてしまう事に気づいていますか?
「他の子供はできるのになんで家の子はできないの!?」という感情が子供に伝わると、劣等感が生まれ最悪の場合、子供が鬱になってしまうこともあります。
発達障害の子供が不登校になるきっかけの多くは中学生時代に生まれてしまうのです。
中学生になって子供の様子が変化した場合、マイナスな発言を抑えてしっかり子供と向き合うことが大切です。
【原因3】発達障害の理解が無い人たちが周りに居る
親や先生が発達障害について理解をしていても、生徒たちが理解できていない場合いじめが発生してしまう可能性が高くなります。
中学時代は心身共に大きく変化する時期なので、周囲と違う考え方をしていたり協調性の無い行動をとっていたりしている人を見るといじめの対象になりやすくなってしまいますね。
先生への理解だけでなく、通っている学校が発達障害についてしっかり理解していなければ発達障害の子供は学校に行きにくくなってしまいます。
発達障害の子供が不登校になった場合の親の対応
不登校になる子供たちは個々に合わせたサポートが必要です。
特に、発達障害のある子供の場合、対応には専門的な知識が求められることもあります。
発達障害の子供に対して親が取るべき対応についてご紹介します。
- 発達障害について理解する
- 学校と協力する
- コミュニケーションをとって話を聞く
- 専門の支援機関や公的機関に相談する
発達障害について理解する
まずは、子供の発達障害について理解することが、適切にサポートする第一歩です。
発達障害は、自閉症スペクトラムや注意欠陥多動性障害などのさまざまな形があります。
発達障害は、学習や社会的なスキルに影響を与えることがあります。
親の対応としては、子供の障害に関する特性を理解し、サポートすることが大切です。
学校と協力する
不登校の子供を持つ親にとって、学校との協力は大切です。
子供の学校での日常生活や、学校で受けられるサポートなどについて、担任教師や学校のカウンセラーと定期的に連絡を取り合うことが望ましいです。
具体的な支援方法や学校生活への復帰についても、学校側と相談しながら進めるようにしましょう。
コミュニケーションをとって話を聞く
親としては、子供が安心して自分の気持ちを話せる環境を作ることが大切です。
子どもに心を開いてもらうためには、圧力を感じさせないような接し方を心がけましょう。
子供が自ら話し始めるまで根気強く待ち、話を聞くことで子供の感じていることを理解することにつながります。
専門の支援機関や公的機関に相談する
さらに、専門の支援機関や公的機関に相談することも有効です。
発達障害支援センターや精神保健福祉センターなどさまざまな機関があります。
支援機関は、具体的な問題解決策を提供してくれる場合があります。
まずは相談することを推奨します。
発達障害の子どもが不登校になった場合の過ごし方
子どもが不登校になったとき、家での時間を有意義に過ごす方法がいくつかあります。
発達障害の子どもが不登校になった場合の過ごし方についていくつかご紹介します。
- 家事を手伝ってもらう
- お散歩に連れて行く
- 生活習慣が乱れないように気をつける
家事を手伝ってもらう
不登校の子どもに家事を手伝ってもらうことは、自己肯定感を高める良い方法となり得ます。
食器を拭く、洗濯物をたたむなど少しだけ家事を手伝ってもらうことは、子どもにとって取り組みやすいはずです。
家事を日常生活の一部に取り入れることで、子どもが自分の役割を感じることにつながります。
お散歩に連れて行く
家に閉じこもりがちな子どもを外に連れ出し気分転換を図りましょう。
散歩や近くの公園へ行くなどで、新鮮な空気を吸うことで心身ともにリフレッシュできるはずです。
違う環境や自然の中で過ごす時間がストレスの発散につながります。
生活習慣が乱れないように気をつける
家にいる時間が増えると、生活リズムが乱れがちになります。
昼夜逆転は子どもの体調にも影響を及ぼすため、規則正しい生活リズムを保つことが大切です。
一定の就寝時間と起床時間を保つようにしましょう。
発達障害で不登校になった子どもの選択肢
発達障害で不登校になった子どもの選択肢についてご紹介します。
- 学校に復帰する
- 転校する
- 高卒認定試験合格を目指す
- 通信制高校に通う
- 就職する
学校に復帰する
今まで通学していた学校に復帰するという選択肢があります。
子どもによっては、元の学校への復帰を望んでいることがあります。
学校側と連携を取りながら、子どもが再び学校生活に戻れるようにサポートすることが大切です。
転校する
全日制の学校が合わない場合には、他の学習スタイルの学校に転校も一つの方法です。
特に定時制高校や通信制高校などは、柔軟な学習スタイルです。
毎日通学が困難な子どもたちにとって適した選択となるはずです。
通信制高校では、自分のペースで学習を進められます。
高卒認定試験合格を目指す
高卒認定試験を取得することで、大学や専門学校への進学ができます。
学校に行かずに、大学や専門学校への進学をしたいという人に適した選択肢です。
高卒認定について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください
通信制高校に通う
通信制高校は、生徒達が無理なく高卒資格を取れるように多様なコースが用意されている場合があります。
全日制高校よりクラス編成が小さいので、しっかり生徒たちに合ったカリキュラムを組んでくれることが特徴です。
通信制高校は集団行動というより、個人の意思を尊重してくれる傾向にあります。
無理なく学習を進められるところが魅力的です。
また、各生徒の好きなことを重点に置いて、個性を伸ばせる学校もあります。
通信制高校は通学日数が少ない学校もあります。
気になる通信制高校があれば資料請求をしてみてください。
就職する
学業を続ける意思がない場合は、就職する道も選択可能です。
働きながら必要なスキルや社会経験を積めます。
ただし、就職には学歴が影響する場合もあります。
将来のキャリアプランをしっかりと考えて行動することが大切です。
発達障害の子供が通信制高校に通う注意点
通信制高校は全日制高校と違い、生徒の状況に対して柔軟に対応してくれる学校です。
しかし、どんなにサポート体制が万全でも通っている子供が不安に感じてしまったり精神状態が悪くなってしまったりしては意味がありません。
通信制高校を通うことを選んだ時は、まず子供と話し合って子供意見に耳を傾けましょう。
通信制高校だから大丈夫だろうと過信していると、子供の意思とは真逆の行動に出てしまい結果悪化してしまう場合もあります。
進学するのは保護者ではなく子供なので、まず子供が通信制高校に進学して何をしたいか聞いてみましょう。
よく通信制高校とサポート校を勘違いしている方もいるので、「どう違うの?通信制高校とサポート校の違いをご紹介」の内容も詳しく読んでおくことをおすすめします!
不登校や発達障害に悩んでいる保護者は1人で悩まない!

不登校や発達障害に悩んでいる保護者は1人で悩まず、支援をしっかり受けましょう。
通信制高校はメンタルケア体制を整えているところもあるので、子供のメンタルケアを考えている人も気軽に相談してみて下さい。
二次障害の合併症を引き起こしてしまうと、状況が悪化してしまうので「もしかしたら?」と思ったらまず子供と相談してカウンセラーを受けて下さい。
発達障害の子供に無理矢理学校に通わせると、状態が悪化して更に塞ぎ込んでしまう可能性があるので注意しましょう。
通信制高校に相談して支援を受けよう
通信制高校は、進学する前に資料をもらうことが可能です。
発達障害の子供を支援してくれる内容も細かく書かれているので、資料請求をして読んでみましょう。
資料内での疑問や質問は通信制高校にお問い合わせすると答えてくれます。
不登校になってしまった子供達が絶対進学できないということはないので、悩んでいる親御さん達はまず通信制高校の資料に目を通してみましょう。
公立と私立の通信制高校ではどのくらい違うのかについて詳しくまとめてある「 私立と公立の学費の違いを徹底解説します!」も参考にしてみましょう!