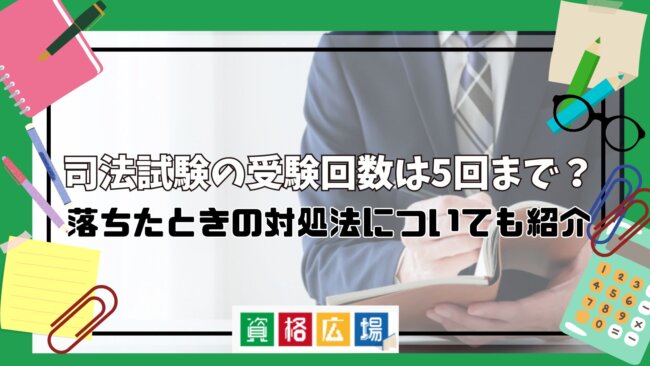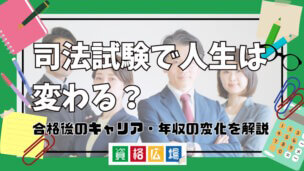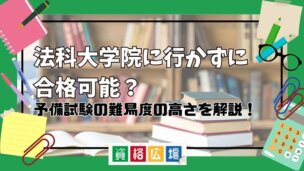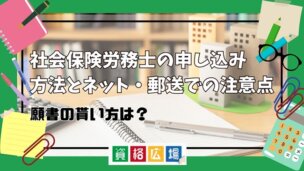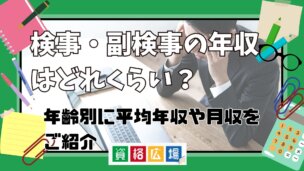「司法試験に受験回数制限があるのか気になる……」
「周りの司法試験受験生が合格までに費やす平均受験回数はどのくらい?」
「何年も合格できずに浪人し続けたら末路は悲惨?」
一生懸命勉強して司法試験に挑戦しても、1度落ちたときのことを考えるととても不安になってしまうものです。
司法試験はみだれ撃ちのように何度も受験できる訳ではなく、受験回数制限があります。
この記事ではなぜ回数制限制度が設けられているのかやその背景、平均受験回数、また次に一発合格するための対処法を詳しく解説します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験一発合格を目指すならアガルートアカデミー!

アガルートは司法試験合格を可能にするカリキュラムを用意している通信講座で、司法試験合格者占有率36%という実績を出しています。
数多くの合格者を輩出しているアガルートで、司法試験合格を狙いましょう!
司法試験は5回まで受けられる
結論から言えば、司法試験の受験回数制限は「5回まで」です。
現在の司法試験の受験資格の取得には「法科大学院を卒業する」か「司法試験予備試験に合格する」かのどちらかですが、どちらであっても受験資格取得後の最初の4月から5年間で5回までと回数制限があることが明記されています。(司法試験法4条1項2号)
以下に新司法試験法の回数制限に関する内容部分を抜粋しました。
(1) 司法試験短答式試験の試験科目
短答式による筆記試験の試験科目について,憲法,民法及び刑法の三科目とする。
(2) 司法試験の受験回数制限の緩和
ア 司法試験の受験できる回数の制限を廃止する。法科大学院課程の修了の日又は司法試験予備試験の合格発表の日後の最初の4月1日から5年の期間内は毎回受験することができる。
イ 特定の受験資格に基づく最後の受験をした日後の最初の4月1日から2年を経過するまでの期間は,他の受験資格に基づいて司法試験を受けることができない旨の規定を廃止する。
このように、司法試験は5年の間であれば毎年受験することができます。
アメリカの場合はLL.Mというロースクールを修了していないと受験資格を得ることができませんが、日本の場合は出来る限り多くの人に門戸が開かれているといえます。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
予備試験は回数制限なく何度も受けられる
また、多くの人は法科大学院ルートではなく予備試験から司法試験に臨むと思いますが、予備試験の受験制限はありません。
1年に1回実施され、受験資格を喪失してしまった人も受験するので、毎年多くの受験者が殺到します。
司法試験に回数制限がある理由
そもそも司法試験にはなぜ回数制限が設けられているのでしょうか?
昔の司法試験制度では受験回数に制限はありませんでした。
法改正前は何度でも司法試験を受験することが可能だったのです。
そこから2006年に1度目の法改正が行われ、法科大学院を修了するか予備試験を合格することで「5年間で3回」まで受験可能となり、そして2015年に現司法試験制度、通称『(新)司法試験』である「5年間で5回」へと変更がなされました。
受験回数を制限した意図や目的、改正案ができた背景についても触れながらご紹介していきます。
受験回数制限の目的①:司法試験浪人を防ぐため
受験回数に回数制限がなかった時代に問題視されていたのが、合格するまで何年も受験し続ける「司法試験浪人」でした。
何年も受験し続ける「司法試験浪人」に早い段階で進路を促すために、平成18年(2006年)司法試験の受験可能な回数を5年間で3回までと制限されたのです。
司法試験浪人の末路は悲惨?三振・五振後は就職するべき?多浪でも逆転合格はあり得るのか解説
受験回数制限の目的②:法科大学院の教育効果を試すため
回数制限がされるようになったもう1つの目的は、法科大学院に関する事情があります。
現在の新司法試験制度における受験回数制限の「5年間」というのは、法科大学院の教育効果が失われることなく最もよく露出する期間であるとみなされ、考案されたものなのです。
受験者同士の過酷な競争を促す為ではなく、法科大学院修了者の多数が合格することを想定して設けられた制限期間であるといえます。
受験回数制限の目的③:受験者のストレスを軽減させるため
回数制限が3回だった時には、受験者の心理的負担やリスクからなる「法曹離れ」や、修了後すぐに受験しない「受け控え」が目立ちました。
そのため、2015年に受験可能な回数制限を現在適用されている5年間で5回までに変更されたのです。
また、受験生の基本的部分の内容理解を深めるため短答式試験の科目も「法律基本7科目」から、憲法、民法、刑法の3科目にしぼられました。
こうした背景から何度か法改正がなされて、今の新司法試験制度になっています。
司法試験の受験回数の制限を超えた時の対処法
5年間で5回という回数制限を超えてしまった場合、いわゆる「五振」となってしまった場合には、受験資格は失われ、司法試験を受けられなくなってしまいます。
しかし、2度と司法試験を受けられなくなる訳ではありません。
再度受験資格を得るには、改めて「法科大学院を修了する」か「予備試験に合格」すれば、再度受験資格を得ることができます。
もう一度受験資格を取得できれば、実質何度でも挑戦することができるといえます。
法科大学院を再度修了する
法科大学院を修了した後に司法試験の回数制限を超えてしまったら、再び法科大学院の入試を受けて修了することで、再度受験資格を得ることができます。
ただし、かかる時間や費用などを考えると、あまりおすすめできる方法ではありません。
予備試験に合格する
予備試験(司法試験予備試験)に合格をして、司法試験への受験資格を再度得る方法もあります。
予備試験は受験資格が設けられていないので、いつでも挑戦することができます。
ただし、予備試験は本番の司法試験並みの学習が求められるので、過去5回の受験で司法試験合格の可能性がほとんどなかった人には、現実的な選択肢ではありません。
司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説
司法試験不合格者の強み
司法試験を残念ながら不合格になってしまった人でも、試験経験者として、別の分野でいかせる強みがあります。
ここからは、主な強みを3つ紹介します。
最高レベルの法知識を持っている
司法試験を受験する過程で得た知識は、法知識としては最高レベルのものです。
法学を突き詰めて考える機会は司法試験受験といった目的がないと難しく、またあらゆる事業で知識を活かせます。
また、一般企業のコンプライアンス部門や、法律事務所の事務職、通っていた資格予備校の職員などは、受験経験者が優遇されやすいです。
インプットの方法やスケジュール管理などのノウハウがある
司法試験対策をおこなう上で、膨大な受験範囲を効率良くインプットする工夫や、1日の中でどのように勉強時間を捻出するかというスケジューリング能力や自己マネジメント能力が育成されているケースは多いです。
こうした能力はどの分野においても活かせるものであり、法曹とは別のフィールドでも大きなアドバンテージになります。
高いレベルの論理的思考力・推論力がある
司法試験では、豊富な法知識をインプットした上で、論文式問題では問題内容に基づいて事態を推測し、適切な回答を論理的に導く能力も求められます。
このような論理的思考力・推論力も、ほぼ全ての分野で活かせるものです。
悔しい経験・努力した経験がある
司法試験合格のために精一杯努力して、その上で不合格になってしまった悔しい経験も、今後の大きな糧になる可能性が高いです。
「法曹の道に進むことはできなかったが、違う活躍したい」という強い思いを持ち続けられれば、周りとは大きな差が付きやすいです。
司法試験が不合格だった場合の再受験以外の方法
①司法書士・行政書士などに目標を変える
司法書士や行政書士など、法律知識が必要な業種に目標を変えるのも手です。
司法試験の対策学習を通して最高峰の法律知識を身に付けたことは、他の難関資格を受験する際も大きなアドバンテージとなります。
②公務員試験を受験する
国家公務員・地方公務員の試験科目の中には、司法試験の科目と重複する部分もあります。
そのため、公務員試験を受験する上で司法試験の学習経験はアドバンテージになります。
ただし、公務員試験には年齢制限が設けられているので、事前に確認をしておく必要があります。
公務員試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安を解説
③民間企業へ就職をする
法曹や公務員のルートではなく、民間企業への就職を選ぶケースもあります。
コンプライアンス部門への配属など、法律知識をそのまま活かせるケースもありますが、司法試験対策で学んだ論理的思考力などは、法律分野以外でも活かすことができます。
④関係性の高い企業や団体へ就職する
司法試験の対策をおこなう上で、ロースクールや勉強会・セミナー、予備校など、様々な場で関係性が出来ます。
こうした団体の中では、司法試験不合格者のために求人を斡旋しているケースもあり、例えば予備校職員や法律事務所の事務職は司法試験経験者が優遇されやすいです。
また、中には知り合った弁護士や同期で司法試験に合格した方からそのまま就職を斡旋されるということも考えられます。
司法試験不合格者のデメリット・注意点
年齢のアドバンテージがない
法科大学院終了後、司法試験を複数回受けるとなると、年齢は20代後半から30代前半になることが多いです。
特に既卒・第二新卒は年齢が若いほうが好まれる傾向にあり、就職で不利になることが多いです。
近年では昔ほど年齢の壁は少なくなっていると言われていますが、それでも不利になる可能性は考慮する必要があります。
職歴がない
年齢相応の職務経験を求められることも多く、多くの司法試験経験者が苦戦しがちです。
司法試験にチャレンジしたという経験で得るものも当然あるはずですが、第三者目線でどれだけ経験を評価されるかについては、企業や採用担当者によって異なります。
司法試験へのチャレンジによって得たものをどうポジティブに伝えていくかの工夫も必要になってきます。
回数制限を超えた後に司法試験の再受験・合格を狙うポイント
もし受験可能な回数制限を超えて「五振」となってしまった場合、一体どうすれば良いのでしょうか。
せっかくコツコツと毎日頑張って勉強してきたのにその苦労が水の泡になるのは、何としてでも避けていきたい現実です。
五振後以降の挑戦も予備試験ルートで司法試験合格を目指すのが一般的でしょう。
しかし、1度ガクッと落ちてしまったモチベーションを再び取り戻すのは至難の業です。
そこでもし司法試験に合格できなければ1度考え直してみたいのが、現在の自分の勉強スタイルです。
2つ紹介するので、自分の状態をチェックしてみましょう。
①勉強方法を見直してみる
そもそも基本的な試験勉強の方法が間違っており、これによって司法試験に落ちてしまうというケースが考えられます。
キーワードは「スキマ時間」と「スケジューリング」です。
通勤・通学時間、トイレの時間、就寝前の時間など、スキマ時間を徹底的に活用して暗記物を行ったり、また「この日までにこの参考書をマスターする」というようにテキストを終わらせる学習計画を立てその通りに実行したりしてみましょう。
小さなことかもしれませんが、意外にこうしたポイントができていない、という人も多く居るのが事実です。
②独学が辛い場合には通信講座を活用する
司法試験は国家試験の中でも最難関の資格として知られています。
科目数も多く、大学などで法律を学習したことがない人などにとっては、独学での対策は非常に厳しいというのが実情としてあります。
そこで活用を考えたいのがオンライン予備校(通信講座)です。
大手の資格予備校に通うのは経済的に厳しいという人も、通信講座なら比較的安価、かついつでも・どこでも勉強でき、プロの手厚いサポートを受けられるため、受講できるならした方が良いでしょう。
司法試験を知り尽くした講師の手を借りることができ、孤独を感じずに勉強ができるというのは、独学者が喉から手が出そうなほど求めているものですよね。
一発合格を目指すための通信講座「アガルートアカデミー」

通信講座を利用するべき、とはいえ、実際には数が多くどれを選んで良いか分からないという人も少なくないはずです。
当サイトでおすすめしているのは、司法試験系の資格に圧倒的な強みを持つ「アガルートアカデミー」。
全幅の信頼を置けるアガルートの司法試験講座を受講するメリットについて紹介していきます。
メリット①:法律の知識ゼロから予備試験合格を狙える
「司法試験どころか、まだ予備試験を受験したことがない」「そもそも法律の勉強を始めていない」という方は、アガルートの「予備試験最短合格カリキュラム」の受講をおすすめします。
予備試験合格に必要な知識やノウハウを習得するための講座をすべて詰め込んだカリキュラムになっているため、受講者にとって最も短い学習期間で試験に挑む力を身につけられます。
「独学で予備試験までたどり着ける気がしない」「効率的な法律の勉強法が分からない」という場合は、高い実績があるアガルートが最適でしょう。
メリット②:合格率が高く信頼できる
アガルートの司法試験・予備試験講座は合格率が非常に高いことで知られています。
令和4年度の司法試験では、全体の合格者1,781名のうち、641名がアガルートの受講生でした。
合格者占有率は36%であり、合格者の半分近くがアガルートを受講していたとなると、かなり信頼が置けるカリキュラムを提供しているといえるでしょう。
司法試験の受験資格を失う前に合格したいなら、ぜひアガルートで対策を取りましょう!
メリット③:充実したテキストで勉強できる
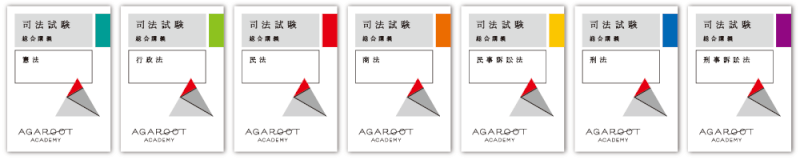
アガルートの司法試験講座のテキストはフルカラーで構成されています。
プロの講師陣たちが作ったオリジナルテキストですので説明も分かりやすく、効率良く勉強することができます。
また、予備試験には論文式試験がありますが、この論文式試験が難関です。
アガルートでは約100通にも及ぶ論文添削を受けることができるため、文章を書くのが苦手な人にとっても有益といえます。
司法試験は受験回数制限に要注意
・予備試験に制限回数はない
・司法試験合格者の司法試験平均受験回数は1.18回
・予備試験合格者の予備試験平均受験回数は2.04回
・回数制限を超えてしまっても再度受験資格を取得できる
・司法試験に合格するにはアガルートアカデミーがおすすめ
こちらの記事では司法試験の回数制限についてご紹介しました。
司法試験は難易度が高く、回数制限も設けられていますが、合格後のメリットを考えれば何度も挑戦する価値のある資格です。
仮に回数制限を超えて五振になっても、もう一度受験資格を得ることが可能なので、決して簡単に諦める必要はありません。
出来る限り最短で合格するためには、アガルートアカデミーの講座を受講することをおすすめします。
「一人では司法試験に合格できるか不安」
「予備試験に一度挑戦したけれど受からなかったから、もう一度やり直したい」
「平均受験回数を超えたくない」
上記のようなお悩みを抱えている人に、アガルートはぴったりです。
詳しく知りたい方は下記のボタンからチェックしてみてください。