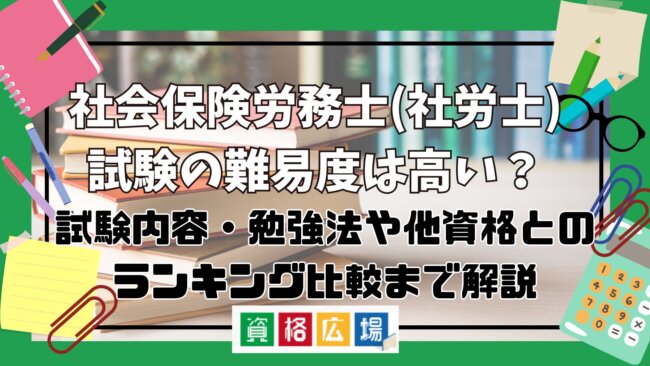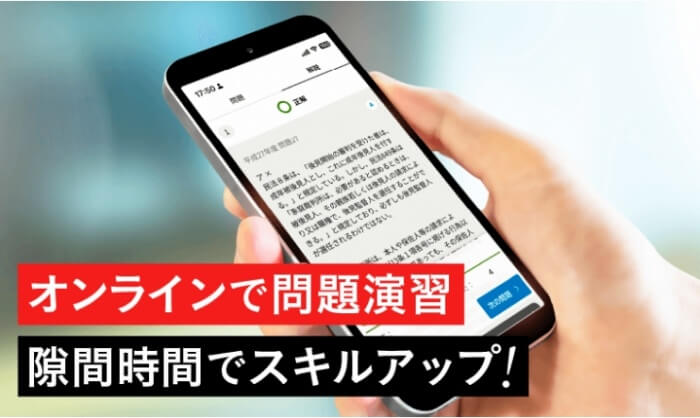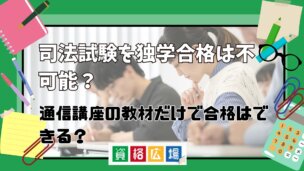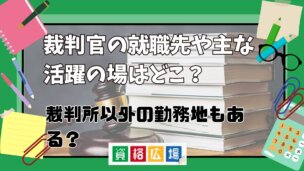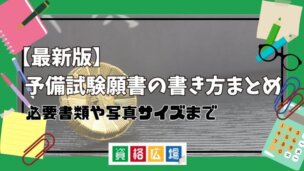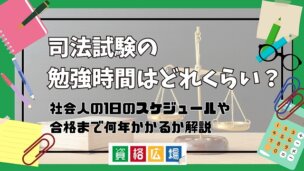社会保険労務士は8士業の一つで社会保険・人事・労務管理の専門家です。
昨今の社会の流れとして働き方改革の推進などに伴い、人事・労務管理の重要性が見直されています。
また、今後も外国人実習生の受け入れ増加や採用ニーズの活発化などから、需要が高まってくると予想される国家資格です。
社会保険労務士の資格を取得したい場合、難易度や勉強時間の目安をあらかじめ把握しておくことで、効率良く合格に向けた勉強を進められます。
社会保険労務士の資格は、ほかの士業(司法書士や税理士など)と比べて取得は難しいのでしょうか。
この記事では、社会保険労務士の合格率や合格に必要な勉強時間の目安など、難易度を他の士業とも比較しながら解説します。また、効率良く勉強する方法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
- この記事でわかること
- 社会保険労務士の試験の難易度
- 社会保険労務士と他士業との難易度の違い
- 社会保険労務士の合格率・受験者数
- 社会保険労務士に合格するための対処法
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社会保険労務士(社労士)の試験難易度
社会保険労務士の試験の難易度は、国家資格の中でもとくに難しくなっています。
記事後半詳しく紹介していますが、合格率はおよそ5~8%程度となっており、約10人~20人に1人程度が合格する割合です。
また、社会保険労務士の試験科目は10科目ありますが、すべてで合格基準点を上回る必要があるのも試験の難易度を押し上げている要因と考えられます。
苦手科目を諦めたり、得意科目に絞って勉強したりする方法では取得できないため、効率良くすべての科目を勉強しなければ取得できない資格です。
社労士試験に働きながら合格することは可能?独学合格は何年かかる?
社会保険労務士(社労士)の合格率
社会保険労務士の合格率は、約5~8%です。
年度によって若干の変動はあるものの、毎年1割に満たない数値となっています。つまり、9割以上の受験者が不合格となっている計算です。
社会保険労務士試験の合格を目指すには、難関資格であることを理解した上で、試験を突破するための勉強を計画的に進めたり、勉強時間を確保したりして臨む必要があります。
社会保険労務士(社労士)試験試験の合格ライン・基準点
令和5年度の社会保険労務士の合格基準点は厚生労働省によって定められています。
- 選択式試験:総得点40点中26点以上、かつ各科目5点中3点以上
- 択一式試験:総得点70点中45点以上、かつ各科目10点中4点以上
合格するためには選択式で6割以上、択一式で4割以上、全体で7割程度の点数が必要です。
特定の科目だけ勉強したり苦手分野を作ったりせず、満遍なく点数を取る必要があると言えます。
ただし、年度によって難易度に差があり上記の基準を元に基準点は変動しているので、全体で7割程度得点できたとしても必ず合格になるとは限りません。
あくまでも合格基準点は参考として確認しましょう。
社会保険労務士の仕事内容や独占業務は?就職先や年収までも調査
社会保険労務士(社労士)に合格するために必要な勉強時間
社会保険労務士に合格するために必要な勉強時間は、800~1,000時間ほどと言われています。
1,000時間で仮定すると、1年で合格するには1日あたりおよそ3時間、半年で合格するにはおよそ6時間の勉強時間が必要です。
普段仕事をしていてあまり勉強時間が確保できない場合は1年以上の時間がかかると思った方が良く、人によっては難易度が高いように感じるでしょう。
ただし1,000時間というのは目安であり、例えば長年人事・労務に従事してある程度の知識が身に付いている方であれば、もう少し短い勉強時間で合格できるかもしれません。
自身の今の知識量や理解力なども考慮しながら勉強計画を立てることが重要となります。
社労士試験の勉強はいつから?勉強時間や順番・スケジュールもご紹介!
社労士試験の試験内容
社労士試験は択一式試験と選択式試験に分かれています。
広い範囲から細かい部分が出題される傾向があり、難易度は高いと言えます。
選択式の対策に重点を置いて、勉強を進めることがおすすめです。
対策が不十分な場合は、合格は難しいでしょう。
2024年(令和6年度)の試験日程
2024(令和6)年の社会保険労務士試験の試験日は、8月25日(日)実施です。
合格発表日は10月2日(水)に行われます。
試験日まで逆算し計画的な勉強をしましょう。
社労士試験が難しいと言われる理由
社労士試験が難しいと言われる、以下の理由を確認しましょう。
- 科目ごとに足切り基準が存在する
- 科目数も多い
- 科目合格制ではない
- そもそも問題の難易度が高い
- 高度な法令理解が求められる
- 紛らわしい選択肢が多い
- 試験時間が不足しがち
理由①科目ごとに足切り基準が存在する
社労士試験では科目ごとに「足切り基準」が存在し、1科目でも足切りに引っかかってしまうと不合格が確定します。
具体的に選択式試験は「各科目5点中3点以上」、択一式試験は「各科目10点中4点以上」という基準があります。
つまり、1つでも苦手科目があって足切り基準に引っかかってしまうと他の科目が満点だったとしても不合格になってしまうのです。
社労士試験で問われる内容は非常に難し1点を取るのに苦労するため、多くの受験生が足切りで涙を呑んでいます。
理由②科目数も多い
社労士試験では下記のように多くの科目を学ぶ必要があります。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
科目数が多く勉強範囲が広いことから、テキストを網羅的に勉強しても理解が不十分になってしまいがちなのです。
特に社会人のように限られた時間の中で勉強をしている方は、全科目を満遍なく勉強するのが難しいでしょう。
このように、科目数の多さ・出題範囲の広さも社労士試験の合格率を低くしている大きな理由です。
理由③科目合格制ではない
足切りの項目でも述べたように、社労士試験は科目合格制ではなく1度の受検で全科目の合格基準をクリアしなければなりません。
他の国家試験を見てみると、例えば税理士試験の場合は科目合格制となっているため1年ごとに各科目の合格を目指すことが可能です。
一方社労士試験の場合は、1度不合格になったらすべての科目を受験し直す必要があります。
たとえ今年度足切りに引っかからなかった科目でも、次年度同様に足切りに引っかからないという保証はありません。
このように、全科目一発勝負である点も合格率が低い大きな理由と言えるでしょう。
理由④そもそも問題の難易度が高い
社労士は社会保険や労務管理のプロフェッショナル資格のため、試験で問われる問題の難易度は高いです。
もちろん中には基本的な難易度の問題もありますが、多くは発展的な内容・応用的な内容の理解が問われます。
そのためテキストの太字部分を覚えるだけでは本試験問題に太刀打ちできず、法令や仕組みを理解することが欠かせません。
特に健康保険法や年金分野は複雑で、理解するのも一苦労です。
「社会保険のプロなら理解して当然」とはいえ、問題の難易度が非常に高い点は押さえておきましょう。
理由⑤高度な法令理解が求められる
社労士では多くの法令の勉強をすることになりますが、いずれの法令でも高度な理解が求められます。
問題を解くためには「なぜ制定されたのか」「誰を対象にしているのか」「例外はあるのか」など、大枠だけでなく内容の理解が必須です。
ただでさえ出題範囲が広い上に高度な法令理解をしなければならないため、勉強の負担も非常に重くなります。
暗記に頼った勉強では安定して得点できないことから、合格率も低くなりがちと言えるでしょう。
理由⑥紛らわしい選択肢が多い
社労士試験は五肢択一式問題と選択式問題がありますが、いずれも紛らわしい選択肢が多いです。
「五択を二択にまで絞り込めたけど正解を絞り込めない!」というケースが非常に多く、理解が曖昧だと失点してしまいます。
前述したように社労士試験で問われる内容は難易度が高いため、正確に理解していないと確実に得点できません。
このように、受験生を悩ませる問題が多く出題される点も合格率が低い大きな理由と言えるでしょう。
理由⑦試験時間が不足しがち
社労士試験は午前の10:30~11:50(80分間)に選択式試験が行われ、午後の13:20~16:50(210分間)に択一式試験が行われます。
一見すると十分な試験時間がありますが、実際に問題を解いてみると「時間が全然足りなかった」という人は少なくありません。
社労士の問題は難易度が高い上に紛らわしい選択肢が多いため、1つの問題を解くのに時間がかかりがちです。
試験時間の終わりが近づくと、まだ手を付けていない問題に関しては満足に取り組めずに終わります。
その結果、得点が伸びずに合格率も低くなってしまうのです。
社会保険労務士(社労士)と他士業の難易度を比較
社会保険労務士は他の士業と比べて難易度に差があるのでしょうか。
社会保険労務士と他士業の令和5年度試験の合格率を比べたところ、以下のようになりました。
| 士業 | 受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 42,741名 | 6.3% |
| 司法書士 | 13,372名 | 5.1% |
| 行政書士 | 46,991名 | 13.98% |
| 税理士 | 32,893名 | 21.7% |
| 弁護士 | 3,928名 | 45.3% |
| 宅建士 | 233,276名 | 17.2% |
| 土地家屋調査士 | 4,429名 | 9.6% |
| 中小企業診断士 | 18,621名 | 5.5% |
社会保険労務士試験の合格率は令和5年度では6.3%で、司法書士や中小企業診断士に比べると高く、行政書士や税理士などに比べると低くなっています。
弁護士の合格率が異常に高く見えますが、試験の受験資格を得るために法科大学院で2〜3年学ぶか合格率3.5%(令和5年度)の司法試験予備試験に合格する必要があり、弁護士試験を受験するまでのハードルがとても高いためです。
ただし社会保険労務士と他士業では試験の受験資格や総受験者数が異なり、一概に合格率と試験の難易度が比例するとは言い切れないので参考程度にしましょう。
社会保険労務士(社労士)の試験科目
社労士の試験は選択式と択一式のマークシート方式です。
選択肢から語句を選んで回答する選択式が40問、出題文に対する正解を選ぶ択一式が70問出題されます。
選択式は40点満点で80分間、択一式は70点満点で210分と長時間に渡る試験となっており、集中力が必要な難易度が高い試験と言えるでしょう。
労働関係科目
労働基準法(選択式3問・択一式7問)
労働者の権利を守るための法律で、労働時間や賃金などに関する知識が問われます。
労働基準法は社会保険労務士試験の基礎となる知識ですので、労働基準法の条文をしっかりと理解することが必要です。
労働安全衛生法(選択式2問・択一式3問)
労働者を危険や健康障害から守るための法律です。
労働基準法に付随する内容ですが、出題範囲が広いため時間を確保して勉強する必要があります。
労働者災害補償保険法(選択式5問・択一式7問)
労働者が業務上の被災や病気に見舞われた際に、国から補償を受けるための法律です。
法改正が少なく、比較的得点を取りやすい科目と言われています。
雇用保険法(選択式5問・択一式7問)
労働者が失業した際に再就職までの生活の保障などに関わる法律です。
制度が複雑で試験範囲が膨大になるので、しっかりと勉強する必要があります。
労務管理・その他の労働に関する一般常識(選択式5問・択一式5問)
労働者派遣法や男女雇用機会均等法など、上記に当てはまらない労務管理に関する法律全般を問われます。
近年の社会の動向などから出題されるテーマを予測して勉強しましょう。
社会保険関係科目
健康保険法(選択式5問・択一式10問)
仕事以外の場面で怪我や病気をした際に、医療費を補助するための法律です。
専門用語が多くボリュームも大きい分野となっています。
厚生年金法(選択式5問・択一式10問)
公務員や会社員が加入する年金制度に関する法律です。
法改正が頻繁に行われてきたため、内容が非常に複雑になっており、十分な理解力が求められます。
国民年金法(選択式5問・択一式10問)
自営業者、会社員、公務員が加入する年金制度に関する法律です。
厚生年金法に比べ基本を理解していれば得点を取りやすい分野となっています。
社会保険に関する一般常識(選択式5問・択一式5問)
社会保険に関する法律全般を問われます。
労務管理の一般常識と同じく近年の動向に注意しつつ、介護保険法など周辺の法律に対する理解を深めましょう。
難易度の高い社会保険労務士(社労士)試験に合格するポイント
社会保険労務士の試験に合格するための対策として意識しておきたいポイントは、以下の3点です。
- 勉強時間を捻出する方法を考える
- 効率良く広範囲の勉強を進める
- 法改正の情報にアンテナを張る
それぞれ具体的にどのような点が試験合格につながるのか、対策しておく効果について解説します。
ポイント①勉強時間を捻出する方法を考える
社会保険労務士の試験に合格するには、勉強時間をどのようにして捻出するかをまず考えることが大切です。
とくに、空き時間に勉強するなど不明瞭なまま計画を立てるのではなく、毎日何時間勉強するのか、何時に勉強するのかをあらかじめ決めておくと良いでしょう。
例えば、朝1時間早く起きて勉強する、通勤時間は用語や法律を記憶する時間に充てる、などです。
また、働きながら勉強する場合は、毎日同じ時間だけの勉強に留めるのではなく「平日は2時間、休日は5時間」など、状況に合わせて勉強時間を変動させる方法もあります。
試験日の1年前から勉強を始めた場合、1,000時間確保するには毎日3時間程度の勉強が必要です。
1日の中でどのようにして勉強時間を捻出するのか、具体的な目標値を設定しておきましょう。
ポイント②効率良く広範囲の勉強を進める
社会保険労務士の試験は科目数が多いため、広範囲の勉強を効率良く進めるのも合格するためのポイントです。
例えば、曜日ごとに勉強する科目を分けたり、1か月後には勉強した範囲の習熟度をチェックする日を設けたりして、勉強範囲を網羅する必要があります。
得意科目や苦手科目だけに集中していると、いずれかの科目で1点が足りず、不合格になるような事態を招きかねません。
効率良く広範囲の勉強を進めていく手段を考え、計画を立てて試験範囲を網羅できるように勉強を進めることが大切です。
ポイント③法改正の情報にアンテナを張る
社会保険労務士は、法律に関する問題が試験で出題されるため、法改正に関する最新情報を把握しておくことも欠かせません。
法改正を把握しておらず、試験で出題されて失点することがないよう、法改正の情報にはつねにアンテナを張っておきましょう。
しかし、個人で情報収集をするには限界があるため、見落としてしまう可能性もあります。
法改正に関する情報は、社会保険労務士資格の通信講座やスクールでも共有してもらえるため、受講しておくのもおすすめです。
ポイント④全科目を満遍なく勉強する
繰り返しになりますが社労士試験には足切りがあるため、苦手科目があると致命的です。
そのため、全科目を満遍なく勉強し苦手科目を作らないことが合格の近道となります。
勉強のスケジュールを立てる際には「全科目をバランスよく勉強する」ことを意識してみてください。
なおもし得意科目がある場合はその科目を勉強する時間を減らして苦手科目を勉強する時間を増やすなど、適宜調整して構いません。
大事なのは「苦手を作らないこと」「足切りに引っかかってしまうリスクを小さくすること」であるため、全科目を満遍なく勉強する意識を持ちましょう。
ポイント⑤法律の目的を理解する
社労士試験の対策では多くの法律を勉強することになりますが、漫然と勉強してもスムーズに理解できません。
そのため、まずは法律が制定された目的を理解し「誰を対象として、何を目的としているのか」押さえると良いでしょう。
基本的に条文の第一条において法律が定められた目的が述べられています。
例えば健康保険法の第一条は「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」です。
つまりこの法律は「業務外のケガや病気、死亡や出産の際に、国民の負担が重くならないようにする」ことを目的としているのだということが読み取れます。
このように全ての法律の第一条を読み、法律の目的や制定された背景を整理してみてください。
ポイント⑥早く正確に解けるようにする
社労士試験は時間との戦いでもあります。
すべての問題に十分な時間をかけて取り組むためにも「早く正確に解く」ことは必須です。
特に、基本的な問題に関しては1分程度で解き、その他の問題にじっくり取り組めるようにしましょう。
早く正確に解くため効果的な勉強法は、十分なインプットと数多くのアウトプットをこなすことです。
また、問題集や過去問を解く際にも時間を気にして回答する意識を持つのも大切です。
ポイント⑧過去問演習を重点的にこなす
過去問は、本試験に対応できるレベルの学力を効率よく習得できる優れた学習ツールです。
そのため、社労士対策の勉強を進める上では過去問演習を重点的にこなすことをおすすめします。
なお過去問は1度解いて終わりにするのではなく、最低でも3回は繰り返し解きましょう。
2回目以降に間違えた問題は「苦手」「理解が不十分」ということになるため、重点的に対策するべきポイントと判断できます。
このように過去問は良質なアウトプットができるだけでなく苦手分野の把握にも役立つため、ぜひ有効活用してみてください。
ポイント⑨寸暇を惜しんで勉強する
寸暇を惜しんで勉強する姿勢も非常に重要です。
社労士試験の勉強で学ぶ内容は難易度が高い上に出題範囲も広いため、寸暇を惜しんで勉強しなければ範囲を網羅できない可能性があります。
また、たとえ短時間でもコツコツと勉強することで勉強のモチベーションが保てるメリットも期待できます。
「学んだ内容を脳に定着させる」「隙間時間を有効活用する習慣を身に付ける」「モチベーションを保つ」という意味でも、ちょっとした時間を活用して勉強することを意識してみてください。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
ポイント⑩社会保険労務士試験の科目免除講習を活用
社会保険労務士試験は下記の条件を満たし所定の講習を受けると試験免除の申請を行うことができます。
- 社会保険労務士事務所の補助者で15年以上の実務経験がある者
- 健康保険組合・厚生年金基金・労働保険事務組合等の役員・従業者で15年以上の実務経験がある者
科目免除講習では労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の徴収等に関する法律、厚生年金保険法、国民年金法、一般常識の中から希望する科目を受講することができます。
1科目につき45,000円で半年間の講習や修了試験を経て受験科目が免除されます。
ポイント⑪社会保険労務士試験の公務員実務経験者免除制度を利用
公務員の方は実務経験があれば科目免除講習を受けずに試験免除を受けることができます。
公務員としての実務経験の内容によって免除される科目に違いがあります。
社会保険労務士試験の科目免除の条件は下記の通りです。
- 労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法に関わる実務経験が10年以上の者は労働基準法・労働安全衛生法の科目免除
- 労働保険事務の実務経験が10年以上になる者は労働保険の徴収等に関する法律の科目免除
- 国民年金法に関わる実務経験が10年以上になる者は国民年金法の科目免除
各条件に当てはまる公務員の方は申請を行うことで試験科目の免除を受けられます。
社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士とは労務管理の業務を請け負う仕事です。
社労士になるためには国家資格の社労士資格が必須です。
社会保険や雇用に関わる労働問題だけでなく、年金制度への理解も求められます。
社会保険労務士(社労士)の仕事内容
労働者と企業の良好な関係を維持するために、きめ細やかな指導やアドバイスを担当します。
以下のように労働社会保険手続に関わる手続きや対応も、労務士の仕事です。
- 社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
- 助成金などの申請
- 労働者名簿調製
- 賃金台帳の調製
- 就業規則・36協定の管理
社会保険労務士(社労士)の平均年収
厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査によると、社労士の平均年収は780.9万円です。
しかし、働く都道府県によっては年収が上下することに注意しましょう。
経済活動が活発でない地方の場合、400万円に満たない年収になる可能性もあります。
社会保険労務士(社労士)の将来性
社労士の業務は減っていくことも予想されます。
人事労務管理ソフトや AIで代替できる仕事は、将来的に減少するでしょう。
国も、労務や社会保険の申請について電子申請を普及させようと注力しています。
今後の将来性を高めたい人は、コンサルティング業務に注力してもいいですね。
助成金の代理申請など、社労士の独占業務に目を向けましょう。
社会保険労務士(社労士)試験の独学合格が難しい理由
社会保険労務士は独学で試験を突破できないかとお考えの方もいるかと思いますが、かなり難易度が高いのでおすすめしづらいです。
理由として以下の3点が挙げられます。
法改正にすぐに対応できない
社会保険労務士試験はその年の4月までに行われた法改正の内容や公表された統計情報を元に出題がされます。
試験は毎年8月に実施されるため、4か月の間に最新の情報を入手して試験対策を講じなければならず、せっかく覚えた制度や条文を覚え直す必要があるかもしれません。
予備校に通ったり通信講座を受講したりすると、即座に法改正に対応した勉強内容を指導してくれますが、独学ではそうはいかないでしょう。
独学すると法改正があったのかどうか、ある場合はどの制度がどのように変わったのかといった細かい情報をキャッチアップしづらく、前年の古い情報のまま試験に臨む恐れがあります。
学習の進捗確認やスケジュール管理がしづらい
「自分がどの範囲まで学習を進められたか」「いつまでにどの範囲を覚えておくべきか」といった進捗確認やスケジュール管理がしにくいことも、独学での合格の障壁になります。
予備校や通信講座では学習内容が明確で、試験日から逆算した履修スケジュールを教えてもらえますが、独学ではすべて自己管理・自己責任です。
勉強の内容を覚えたり過去問を解いたりする時間に加え、自分で進捗状況と日程の確認・調整をするための時間も取る必要があり、思うように学習が進められないという懸念が残ります。
途中で挫折しやすい
スケジュール管理がしにくかったり切磋琢磨する仲間がいなかったりとった理由から、一人で勉強していると試験を受ける前に挫折してしまいやすいです。
特に分からない箇所が出てきた場合、すぐに質問できないと解決に時間がかかり、効率よく学習が進められずに難易度が高く感じて心が折れることが危惧されます。
何度も受験していてもう少しで合格できそうな方であれば別ですが、社会保険労務士試験の勉強をしたことがない方は予備校や通信講座を利用することをおすすめします。
通信講座を使って社会保険労務士試験合格を目指したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
アガルートの『社労士』講座の評判は?合格率や費用について調査
社会保険労務士(社労士)試験ならアガルート

社会保険労務士(社労士)試験に挑戦するのなら、大手通信講座の1つであるアガルートアカデミーがおすすめです。
アガルートではプロの講師が重要なポイントを分かりやすく教えてくれ、初めての方でも最短で合格を目指せる講座をしてくれます。
また、完全オンライン講座となっているので、好きな時間と場所で勉強をすることができます。
全国平均の4.46倍の合格率
アガルートは令和5年度の社労士試験で、全国平均の4.46倍の合格率である28.57%という高い実績数を出しました。
合格した受講生の中には、仕事と子育てを行いながら勉強し合格した方や、まだ20歳で1発合格した現役大学生の方まで、様々な方がいます。
高い実績数と、受講生1人1人に最適な学習カリキュラムを組んでくれる充実したフォロー制度も、アガルートの大きな強みと言えるでしょう。
場所を選ばず問題演習に取り組める!「オンライン演習サービスTOKERUKUN」スタート!
大手通信講座アガルートアカデミーは、移動中のちょっとした隙間時間を有効活用できるサービスとして、「オンライン演習サービスTOKERUKUN」という『社労士試験』の対策講座サービスを開始しました。
「オンライン演習サービスTOKERUKUN」は、忙しい日々の中で資格試験の準備を進めたい方に最適なサービスです。
このプラットフォームを使用することで、ユーザーはいつでもどこでも択一式の過去問題に挑戦できます。
特に移動中やちょっとした休憩時間など、日常のスキマ時間を活用して効率的に学習を進めていきたい方におすすめのサービスです。
このサービスは、スマートフォンに最適化されており、その使いやすさから多くの学習者に支持されています。
パソコンやタブレットでもアクセス可能で、学習者のニーズに柔軟に応えています。
【「オンライン演習サービスTOKERUKUN」の利用手順】
- 問題演習システムにログインする
- 演習する問題を選択する
※TOKERUKUNの問題は、「科目」>「分野」>「単元」>「問題文」のように分かれています。 - 問題演習を行う
- 問題演習を終了する
登録者は、専用のアプリケーションをダウンロードし、自分のアカウントでログインするだけで、すぐに問題演習に取り組めます。
また、「TOKERUKUN」では、各問題に対する詳細な解説も提供されており、単に問題を解くだけでなく、その解説を通じて理解を深められます。
これにより、試験の出題パターンや頻出ポイントを効率的に把握し、実際の試験でのパフォーマンス向上が期待されます。
社会保険労務士(社労士)試験は難易度が高いため対策が必要
本記事では社会保険労務士の難易度・合格率について解説してきました。
本記事の内容をまとめると下記の通りになります。
- 社会保険労務士の合格率は6〜7%台
- 試験に合格するために必要な勉強時間は800〜1,000時間
- 試験の難易度は高いが、しっかりと勉強すれば弁護士や司法書士など他の士業と比べると合格しやすい
約1,000時間の勉強時間を確保する必要があることや合格率が6~7%代ということから、難易度としては難関資格に分類されます。
しかし受験資格を得ることが難しい弁護士や、膨大な勉強時間が必要な司法書士などの士業に比べて難易度は低い傾向にあると言って良いでしょう。
社会保険労務士は社会からのニーズが高い士業ですので、目指す価値は高いです。
キャリアアップ・独立開業などを今後の目標としており、社会保険労務士を目指したい方は是非この記事を参考にしてみてください。
行政書士・司法書士・社労士の違いとは?資格取得の難易度も比較
監修者情報
吉村 徳男
経営企画本部長/特定社会保険労務士

全国展開を進める当法人は、グループ全体で1,000超の顧問先を抱え、蓄積された課題解決力が最大の持ち味です。「何が企業にとって最善なのか」を問い続けることをモットーに、人事労務全般を手掛ける「社外人事部」として、社長を全力で応援します!
所有資格等
特定社会保険労務士
公式サイト:https://kyoshin.group/