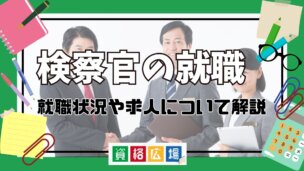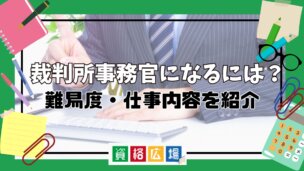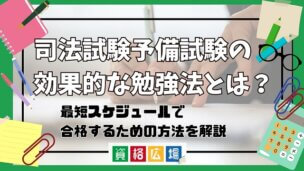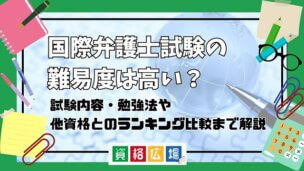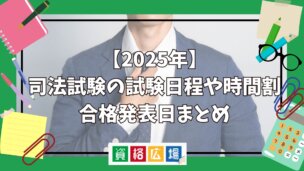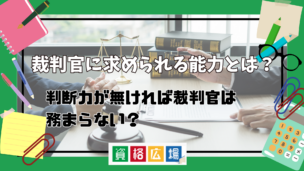弁理士とは知的剤再建に関する法的な仕事をおこない、おもに特許や商標、意匠を特許庁に申請したりします。
弁理士になるには一般的に弁理士試験への合格が必要であり、合格率は例年6%程度で推移しています。
また弁理士試験には受験資格がなく、学歴や年齢関係なく誰でも受験することができます。
今回は弁理士になるまでの段階や弁理士の仕事内容、試験の難易度などについて詳しくご紹介します。
これから弁理士を目指す方や興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
弁理士になるには
弁理士になるには、経済産業大臣から指定された機関で実務研修を受け、研修後に日本弁理士会に弁理士としての登録をする必要があります。
ここでは、便利になる手順についてご紹介します。
➀弁理士試験への合格
弁理士になるためには、まずは弁理士試験に合格する方法が挙げられます。
弁理士試験は、弁理士として必要な学識および応用能力を有しているかを判断するための試験です。
弁理士試験では広範囲の法律知識だけでなく、知識を応用して問題のポイントを的確に把握し、的確な回答を導き出す応用力も問われます。
受験資格に制限はなく、学歴や国籍、年齢などによる制限はあありませんが、例年合格率は6%程度とかなり難易度の高い試験となっています。
弁理士試験は一次、二次、最終の3段階で構成されており、それぞれ短答式試験、論文式試験、口述試験が行われます。
合格基準を満たすことで次の試験に進むことができるスタイルです。
また弁護士資格を持つ方や、7年以上特許庁の審判官または審査官として審査や審判の事務に従事した方は、実務修習を修了することで弁理士資格を取得することもできます。
②実務研修を受ける
弁理士試験に合格後、弁理士として登録するためには、実務修習を修了しなければなりません。
実務修習は弁理士法によって定められた研修で、弁理士試験で身に付けた知識を実務として活かせるかや弁理士としての専門的応用能力を習得することが目的です。
実務修習は、毎年一度日本弁理士会が行っており、実務修習を修了することで弁理士登録に進むための証明書を取得できます。
また弁理士試験に合格した者ならば誰でも受けることができ、一次試験合格者は実務修習の参加資格を得ることができます。
修了証書は、弁理士としての専門的な能力を証明する重要な資格となるので紛失などには注意しなければいけません。
実務修習の内容については、弁理士会が定めたテキストや課題をもとに行われ、ウェブ講義システムを利用し、事前に学習した内容に基づいて課題を提出し集合研修が実施される流れとなります。
集合研修は、会場によって曜日や時間が異なりますが、例えば隔週土曜日のコースでは、朝9時から夕方5時まで行われることがほとんど。
集合研修では、ウェブ講義で学んだ内容の理解を深め、実務に活かせるようにするための講義や演習が行われます。
すべての集合研修に参加し、各科目の課題を期日までに提出する必要があります。
提出した課題は講師によって採点され、合格点に達していなければ再提出する必要があります。
なお実務研修修了には、118,000円の受講料が必要となるほか、交通費や宿泊費など、追加の費用がかかるケースもあります。
③弁理士登録を行う
実務修習の修了証書を取得したら、弁理士として登録手続きを行い、登録手続きを完了すると、「弁理士」としての資格が正式に認められます。
反対に弁理士試験に合格して実務修習を修了していても、弁理士登録をしなければ「弁理士の独占業務」を行うことはできないので注意が必要です。
弁理士登録手続きは日本弁理士会に対して行い、申請は持参または郵送によって手続きします。
弁理士登録には合計で110,800円が必要となり、内訳は登録免許税が60,000円、登録費用が35,800円、登録月の会費が15,000円です。
さらに様々な書類の準備や郵送費などの費用が別途必要となります。
登録申請書類を提出すると、日本弁理士会で審査が行われます。
通常、審査には10日ほどの期間がかかりますが、実務修習が終了した直後は多くの登録申請が集中するため、審査には2週間程度かかるといわれています。
弁理士試験への合格以外に弁理士になる方法
弁理士試験への合格、実務試験と登録によって弁理士になるのは一般的なルートですが、ほかにも弁理士になる方法はあります。
弁理士は原則、司法試験に合格して司法修習を修了した人や特許庁で審判官または審査の事務に一定期間(通算7年以上)以上従事している人であれば弁理士となる資格を持つ者として認められます。
弁理士試験を受験することなく実務修習を修了し、登録手続きを経ることで弁理士になることができます。
弁理士試験に受験資格はない
弁理士試験の概要を下にまとめました。
| 受験資格 | 特になし(年齢・国政・学歴による制限なし) |
|---|---|
| 年間試験回数 | 1回 |
| 受験料金 | 12,000円 |
| 願書提出 | 3月中旬~4月中旬 |
| 受験票発送 | 5月上旬~中旬頃 |
| 短答式筆記試験 | 5月中旬~下旬 場所:東京・大阪・仙台・名古屋・福岡 |
| 論文式筆記試験 (必須科目) | 6月下旬~7月上旬 場所:東京・大阪 |
| 論文式筆記試験 (選択科目) | 6月下旬~7月上旬 場所:東京・大阪 |
| 口述試験 | 10月中旬~下旬 場所:東京 |
| 合格発表 | 6月上旬(短答式) 9月中旬(論文式) 10月下旬~11月上旬(最終発表) |
弁理士試験は年に1回、願書提出を含めると3月~11月まで半年以上をかけて長期間行われます。
試験の種類は短答式・論文式・口述式の3種類です。
また、受験資格は特に定められてなく、年齢・学歴・性別に関わらずだれでも試験を受験できます。
ここでは、それぞれの試験ごとに詳しく試験内容をご紹介します。
短答式試験
短答式試験ではおもに特許・実用新案・意匠・商標・工業所有権に関する条約・著作権法・不正競争防止法などから、5肢択一式の問題が60問出題されます。
全体の65%以上の正答率で合格となっています。
また5分野に分かれている問題に対して各分野で最低40%以上正解する必要があるため、入念な準備が必要です。
論文式試験
論文式試験は特許・実用新案・意匠・商標の必須3科目に加え、法律や理工科目の内1科目選んで回答する試験です。
法律の知識だけでは対処できない仕事を担当することも珍しくないといった背景から、選択科目として理工系科目からも選べるようになりました。
必須科目の合格基準は100点満点で平均54点程度ですが、47点未満の科目があると不合格になるため注意が必要です。
論文式試験では不得意科目を作らないようにするのが試験突破のコツとされています。
また論文式試験は2時間と1.5時間の2種類あり、日頃から時間内で論文をまとめる練習をしておくことも大事です。
口述式試験
口述試験は特許、実用新案・意匠・商標の3科目から口頭で出題される面接方式の試験で、2科目以上の答えが不十分だと不合格となります。
合格率が96.4%と高めですが油断は禁物です。
なぜなら、これまでの試験形式(ペーパー試験)と違い、試験官2名と問答すること、1科目10分という制限があるなど普段とは違うシチュエーションだからです。
質問に対して正しくこたえられるよう、模擬面接や第三者に観てもらうなど面接慣れをしておくと安心できるでしょう。
弁理士の選択科目の内容と選び方は?免除を受けられる科目もある?
弁理士試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
弁理士試験の難易度・合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 3,160人 | 191人 | 6.0% |
| 令和5年 | 3,065人 | 188人 | 6.1% |
| 令和4年 | 3,177人 | 193人 | 6.1% |
| 令和3年 | 3,248人 | 199人 | 6.1% |
| 令和2年 | 2,947人 | 287人 | 9.7% |
令和2年を除いてここ5年の弁理士試験の合格率は6%程度で推移していることが分かります。
他の士業の中でも弁理士試験は司法書士・社労士の次くらいに難易度が高い試験と言われています。
先ほども述べたように平均受験回数が2回以上であることも踏まえると、独学だと難しいでしょう。
弁理士試験の勉強時間の目安
弁理士試験の勉強時間は初めて弁理士の勉強をする方で3,000時間必要と言われています。
1年で弁理士になるには、少なくとも1日に8時間以上勉強しなくてはなりません。
厳しさから試験勉強を途中で断念してしまう方も少なくないようです。
ほかの国家試験と弁理士試験の難易度を比較
弁理士試験は、他の国家試験と比較しても6%程度とかなり難易度が高いことで知られており、7士業の中では司法書士・社会保険労務士(社労士)・弁護士に続いて難易度が高い試験といわれています。
なお以降は土地家屋調査士・行政書士・税理士・海事代理士の順になるとされています。
しかしあくまで国家試験のみを比較したときのランクであり、合格率だけではなかなか判断しきれないのが現状です。
受験資格を取得するための試験や学校での学習が必要なものもあります。
⇒「弁理士試験の難易度は高め!文系では不利?必要な勉強時間や収入も紹介」
⇒弁理士資格は働きながら取得可能?実務実習は休職しないと無理?」
弁理士になれない人の特徴・条件
以下の特徴に当てはまる人は、弁理士試験に合格して実務修習を受けて登録しても弁理士にはなれないので注意が必要です。
➀刑事処分を受けた
過去に禁固刑を受けたことがある、もしくは所定の刑事処分を受けてから所定期間以上経過していない場合、弁理士登録を受けられないので注意が必要です。
刑事処分を受けるケースとして挙げられるのは以下のものとなります。
- 禁固以上の刑に処せられた者
- 弁理士法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、又はその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 関税法、著作権法、半導体集積回路配置に関する法律又は不正競争防止法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
➁業務上の処分を受けた
たとえば公務員や士業において業務上の懲戒処分等を受けて、処分から所定期間以上経過していない人もまた弁護士登録を受けられません。
具体的には以下のケースが挙げられるので、該当する方は3年もしくは停止間を過ぎてから受験することをおすすめします。
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、処分から3年を経過していない
- 弁理士法第23条第1項の規定により弁理士登録の取消しの処分を受け、処分から3年を経過しない者
- 弁理士法第32条の規定による業務の禁止の処分を受け、処分から3年を経過しない者
- 弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受け、処分から3年を経過しない者
- 弁理士法に定める業務の停止の懲戒処分を受け、停止期間中に弁理士登録が抹消されて、停止期間を経過しない者
➂制限行為能力者である
制限行為能力者とは、私法上の法律行為を単独で完全におこなうことがで着ない人のことを指します。
おもに以下の条件に当てはまる人が挙げられます。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
弁理士とは
弁理士とは知的財産の専門家として主に特許出願に関する書類の作成や申請の代理を行う職業です。
そもそも知的財産とは小説や音楽、絵画などの著作物や、企業のブランドロゴなどの商標を含む、「人間の知的活動によって創出された、経済的価値を有するアイデアや創作物」を指します。
弁理士はそこで知的財産に関連する法律の専門家として、権利侵害の防止や保護に関するさまざまな手続きを担当します。
弁理士が勤務する場所にはおもに特許事務所や企業の知的財産部門が挙げられます。
ほかにも、特許事務所や企業での経験を活かして独立開業する弁理士も存在します。
弁理士の仕事内容
ロゴや会社名、本や技術発明など人のアイデアから生み出されたものを知的財産と呼び、その中でも特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは産業財産と名付けられています。
弁理士の仕事はそれらの産業財産含む知的財産の保護、適正な利用・運用から相談まで、知的財産に関する幅広い業務を行うことです。
弁理士の仕事内容を「産業財産権の取得」「産業財産権の紛争の解決」「知的財産に関する相談」の3つに分けてそれぞれご紹介していきます
仕事内容①産業財産権の取得
弁理士は、新しく出来た技術やオリジナリティ性があるものに「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」など、オリジナリティを保護するための権利を申請する仕事を行います。
申請時に特許庁に申請しなければいけない明細書などの出願書類の作成も弁理士の仕事内容の1つです。
特許を申請するまでのプロセスは複雑で専門的な知識が求められるので、一般の方が独自で行おうとすると大きな時間と苦労を伴います。
弁理士は企業や個人からの特許申請の仲介を行って、知的財産が守られるように事務手続きを行うのです。
明細書とは?申請するアイデアに関する市場の動向や知識を調査し、申請するものがどれだけ新しく価値のあるものか書面にまとめたもの
仕事内容②産業財産権の紛争の解決
一度特許を申請したとしても、特許保持者に断りもなく使用されるという紛争・トラブルも珍しくありません。
紛争・トラブルになってしまった時に、当事者の間に入って解決するのも弁理士の仕事内容の1つです。
解決方法としては裁判などがあり、最近では日本国内ではなく海外企業とトラブルになるケースが多く言語などの国際力も試されるようになって来ています。
仕事内容③知的財産に関する相談
弁理士は特許申請やトラブル解決が主な業務内容と認識されていますが、特許に関する相談に乗ることも弁理士の仕事内容の1つとして挙げられます。
弁理士には様々な依頼や相談を持った顧客が来るので、専門知識を活かしてコンサルティングを行います。
顧客に特許などに関する最適なアドバイスが出来るように務めるのも弁理士の仕事となっています。
弁理士の平均年収
厚生労働省のデータによると、弁理士の平均年収は1121.7万円となっています。
平均年齢が51.2歳であることから、年齢を重ねることによって上がっていくことが分かります。
しかし平均年収が400万円程度とみるとかなり高い水準であるといえるでしょう。
また大手企業に勤務する場合と中小企業では200~300万円程度の差が生まれることもあり、さらに独立開業すれば1,000万円以上を若い時からでも達成できるケースもあります。
ま理士は男女間の年収差はほとんど見られない傾向にあるため、女性でもライフスタイルの変化があってもくいっぱぐれないのも魅力です。
弁理士の平均年収は一般的な給与所得者よりも高いとされていますが、平均に達しない人も多くいることを念頭においておきましょう。
弁理士に年齢制限はある?年齢分布や合格者・引退者の年齢まとめ
弁理士の将来性
弁理士は特許に関する専門的な知識を持つ職業であり、将来的に有望なキャリアの一つとされています。
特許庁の発表によれば、日本国内の特許出願件数は年々減少しているといわれています。
弁理士の主な業務は知的財産権の出願手続きであるため、国内市場における需要は減少傾向にあります。
一方で、日本の特許庁を受理官庁とする特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)の件数は2019年までは増加しており、依然として高い水準を保っています。
研究開発や企業活動の国際化が進む中で、国際的な視点からも弁理士の需要は増加しています。
また、最近では企業の知的財産部門や法務部門で働く企業内弁理士の必要性が高まる傾向にあります。
企業内弁理士の主な業務は、特許、商標、ライセンスに関連する契約業務です。
企業内弁理士は従来、外部の特許事務所に委託されることが一般的でしたが、最近ではコスト削減を目的に自社での申請を試みるケースが増加しています。
内閣府が企業に対して知的財産や無形資産を活用し競争力を向上させるよう促していることもあり、企業内弁理士はますます重要な職業として注目されると予想されています。
弁理士試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
弁理士資格を取るならアガルート

ここまで弁理士試験の難易度について説明してきましたが、独学では厳しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方はアガルートの通信講座がおすすめです。
アガルートは難関国家資格を専門に扱う通信講座で、難しい資格試験でも高い合格率を誇ります。
| 学習形式 | 通信講座 |
|---|---|
| コース | 総合カリキュラム(民法オプションあり):215,820円 総合カリキュラム(民法オプションなし):176,220円 短答カリキュラム:146,520円 |
| 特徴 |
|
| サポート |
|
| 合格率 | アガルート受講生の27.08% |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
全国平均約4.5倍の合格率の高さ

全体の合格率が低い弁理士試験ですが、アガルート通信講座の受講者の令和6年度の合格率は27.08%と驚異の合格率を誇っています。
これは弁理士試験の全体の合格率6.0%に対して4.5倍です。
合格実績の高さからも、アガルートの学習カリキュラムや講師陣の指導の質の高さが分かります。
弁理士資格を取得するには弁理士試験への合格がほとんど!
今回は弁理士になるまでの段階や弁理士の仕事内容、試験の難易度などについて詳しくご紹介してきました。
弁理士になるには弁理士試験への合格から実務修習の修了、弁理士登録といった流れが一般的です。
ほかにも、弁護士の資格を持っていたり、特許庁において審判又審査に所定期間以上従事している場合でも弁理士を目指せるケースがあります。
弁理士試験は例年10%を切るなど、国家資格の中でもかなり難易度の高い試験となります。
平均受験回数は3~4回なので、今回の記事を参考に計画的に勉強スケジュールを立てて弁理士試験合格を目指してみてください。