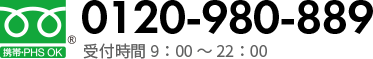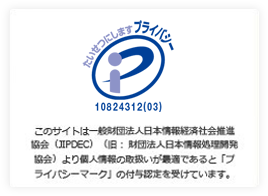小学生でも不登校になる!不登校の要因とその対応方法! 更新時間 2026.01.08
小学生の子どもを持つ保護者の中には
- 小学生の子どもが不登校になってしまい、どうしたらいいのか分からない
- 卒業はしてほしいけど、この先中学校・高校と不登校にならないか心配
- 無理はさせたくないけど、将来を考えると勉学だけはしてほしい
というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
実際、小学生という多感な時期に、ほんの些細な要因から不登校になってしまう子どもが増加傾向にあるのも事実。
今回は、そんな小学生の子どもを持つ保護者の方に向けて「小学生が不登校になってしまう要因とその時の対応方法」についてお伝えいたします!
小学生特有の不登校になってしまう要因
保護者の方は、お子様が不登校になってしまった要因は把握できていますか?
実は、不登校というくくりでも、その要因によってとるべき対応も変わってきます。
ここからよくある小学生の不登校の原因を紹介していくので、子どもが当てはまるか確認してみましょう。
環境の変化によるストレス
小学校に入学すると、それまで通っていた幼稚園や保育園とは大きく異なった生活リズムで、生活を送ることになります。
そのため、環境の変化によって不登校になってしまう小学生は少なくありません。
環境変化におけるストレスの要因としては、主に3種類に分けることができるので、ここから説明していきます。
①両親と長い時間離れることに対するストレス
今まで当然のように一緒に生活をしていた両親と、長時間離れることになると、多くの子どもは不安を抱えてしまいます。
また、その不安に慣れることができない子どもも少なくありません。
不安感が大きく、環境に適応することができなかった子どもが不登校になってしまうこと傾向があります。
②規則正しい集団生活に対するストレス
小学校に入学すると、決まった時間に登校し、決まったクラスに所属することになります。
大人でも新しい環境に適応するまでは時間も必要になり、ストレスもかかりますよね。
子どももそれは同様で、新しい環境に適応するまではストレスを感じていることが多いです。
③人間関係の変化に対するストレス
小学校に入学すると関わる人の数が格段に増えます。
クラスの人数も増えることで、先生が見ることのできない場面も増えるため、自立することが求められるでしょう。
最初の友人作りに失敗してしまうと、自分の殻に閉じこもってしまい、その後もうまくいかなくなる生徒も少なくありません。
また、うまく友人関係を築けていたとしても、何かトラブルが原因となりいじめなどが発生すると、それが原因で不登校になってしまうことも考えられます。
学業不振
小学校に入学すると決まった時間に勉強が行われます。
はじめは、先生も子どものペースに合わせて授業を行ってくれますが、ついていけない子どもにとってはこれもまたストレスの原因となってしまうでしょう。
学業不振におけるストレスの要因としては主に2つ挙げられます。
①授業中に集中力がもたず、勉強に追いつくことができない
小学校では主に黒板を使って授業を受けることになりますが、集中力が持たないと板書が間に合わず、徐々に勉強についていけなくなる場合があります。
こちらも環境変化と同じく、多くの子どもは徐々に対応していけるようになりますが、中には対応しきれずについていけなくなってしまう子どもがいます。
一度ついていけなくなってしまうと、授業で行っている内容を理解できず、さらについていけなくなってしまう悪循環に陥ってしまう生徒も少なくありません。
分からない授業を長い時間聞いていなければいけない状態は、大きなストレスとなって不登校の原因となってしまう可能性があります。
②他の生徒と成績を比較される
こちらは勉強についていけなくなるのではなく、テストの点数や成績などを比較されることそのものがストレスになっているケースです。
保育園や幼稚園ではテストなどはほとんどなかったのにも関わらず、小学生になるとテストを受けるため、その点数で優劣がつき比較されることもあるでしょう。
中には親の期待に応えなければなれないというプレッシャーがストレスとなり、勉強から逃げ出したいという気持ちから、さらに成績が落ちてしまうという状況になってしまうことがあります。
病気・発達障害などの特性
不登校とは「病気や経済的理由以外での長期欠席」と定義されてはいますが、実はその中でも見つかっていない病気や障害を抱えた子どもがいることがだんだん分かってきました。
不登校の原因となりうる病気や障害は、以下のようなものを挙げることができます。
- うつ病
- 不安症
- 発達障害
また、病気や障害ではないですが、最近SNSで話題になっているHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)も不登校になる原因の一つであるといわれています。
HSPとは、簡単に説明すると「周囲の刺激や環境の変化にとても敏感に反応してしまう」「他の人の些細な動きにでも反応してしまう」といったような特性を持った人のことです。
周囲に気づかれていなくとも、上記のような病気、特性を持った子どもは不登校になってしまう傾向があります。
発達障害を抱えている子どもが不登校になってしまう原因については、「発達障害の子どもが不登校になってしまう原因と解決法を紹介!通信制高校なら無理なく進学できる」という記事も合わせて読んでみて下さい!
学年別の不登校になる主な要因
小学校は6年間と義務教育期間内で最も長く所属する場所となるため、年齢によって不登校の原因が変化してくるのが特徴です。
先ほど説明したストレスの原因を用いて、学年別に不登校の原因を説明していきます。
小学校低学年(1,2年生)
小学校1.2年生の不登校になる最も大きな原因が、環境の変化によるストレスです。
その中でも「両親と長い時間離れることに対するストレス」が不登校の大きな原因であるといわれています。
小学校入学に伴いそれまでの日常生活が一変することに合わせて、両親という心の拠り所から離れなければならないストレス・不安が原因となり、不登校になってしまうケースは少なくありません。
小学校中学年(3,4年生)
小学校3,4年生の場合では対人関係や学習面に関するストレスが主な不登校の原因となります。
中学年になると仲の良い何人かのグループができるようになり、より親密な付き合いをするようになるでしょう。
すると、些細なトラブルから、人間関係に亀裂が入ってしまうケースも多くなります。
また、グループ内でのテストの点や成績の優劣が把握できるようになり、そこにショックを受け、それがストレスとなり不登校になってしまう可能性も高いです。
小学校高学年(5,6年生)
小学校5,6年生の場合は、これまでとは一気に毛色が変わり、思春期や親への反抗心が不登校の原因となることがあります。
この時期の子どもは、自分の身体や心の成長に敏感になり、友人との些細な違いが気になってしまい、それがストレスとなるケースが多いです。
さらに反抗期に入ると、それまでは友人関係や学習面で問題がなく、いわゆる優等生と呼ばれていた子どもでも親に対して反発するようになる可能性もあるでしょう。
また、家庭内で両親の不和や不倫などの家庭環境がきっかけとなり、不登校になってしまったという前例も少なくありません。
子供に対して親ができることは?
ここまでで、お子様が不登校になってしまった原因は分かりましたか?
ここからは子どものために、保護者がしてあげられることをご紹介いたします。
また、もっと詳しく知りたい方は「不登校や引きこもりの親が実はやってはいけない行動6つ」という記事も確認してみて下さい!
子どもの考えと正面から向き合う
前提として、不登校になってしまったお子様は、大きな不安やストレスを抱えています。
そのため、まずは子供と向き合って話を聞いてあげることが大切です。
正直、最初は子どもの本心を聞くことができないかもしれません。
しかし、毎日5分間だけでも良いので、子どもとだけ向き合う時間を作ることで、次第に子どもは心を開いてくれるでしょう。
また、子どもが話をしてくれるようになったら、以下の3点だけを注意するようにしてください。
- 子どもを否定しない
- 説得をしない
- 興味を持って話を聞く
話を聞いているうちにアドバイスをしたくなると思いますが、ここではとにかく「子どもの話を聞く」ということを優先しましょう。
子どものことを肯定してあげる
子どもが不登校になってしまうと、最初は親として「何とか学校に行ってほしい」という気持ちになることもあると思います。
しかし、ここで学校に行くということを強制することは、不登校の解決においては遠回りになってしまうでしょう。
また、子どもの自己肯定感を高めてあげることも大切です。
学校の勉強以外でも、子どもの興味のあることや、やりたいことをやらせてあげることで自己肯定感を高め、将来について前向きに考えるきっかけを与えてあげましょう。
子どもに居場所を作ってあげる
学校と家庭以外の第三の居場所を作ってあげることも、非常に有効です。
直接学校に復帰することが難しい場合でも、不登校の子どもに向けた支援施設はたくさんあるので、気になる方は一度自治体に問い合わせてみましょう。
また、子ども自身が学校に復帰したいと思い始めた時に考えていただきたいのが、学校に信頼できる先生や友人を作っておくことです。
こうしておくことでスムーズな学校復帰や、復帰後の継続的なサポートを受けることが可能になります。
まずは子どもに合った対応を心がけよう
今回は小学生が不登校になってしまう主な要因と、保護者の対応、支援施設をご紹介させていただきました。
小学生でも大人でも環境の変化や人間関係に悩んでいることは変わりません。
そして、小学生の不登校には子どもに合った対応をしてあげることが重要になります。
ぜひこの記事を参考にお子様の人生の選択肢を広げてみてください!
中学生の不登校についてもっと知りたいという方は「中学生の不登校は環境の変化が原因!対策について詳しく解説」をチェックしてみましょう。