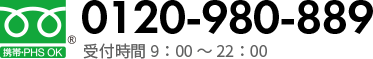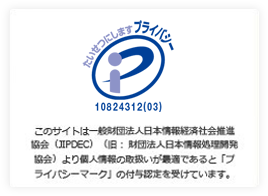不登校の小学生と中学生と高校生の違いとは?要因と対応方法を解説 更新時間 2026.01.08
不登校とは、学校に登校しない状態のことを指します。
まったく学校に行かない場合もありますし、たまに登校する、保健室登校をしている(授業を受けていない)という場合もあるでしょう。
文部科学省では「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にある為に年間30日以上欠席した者の内、病気や経済的な理由による者を除いた者」と定義されています。
ただ、学校に行けない/行きたくないという気持ちを抱えている子どもであれば、年間30日以上欠席したかどうかに関わらずなんらかの対応をしていくべきです。
不登校の原因はさまざまですが、本記事では小学生と中学生と高校生が不登校になる要因とその違いについて解説していきます。
本記事で分かること
- 不登校の小学生・中学生・高校生の現状と違い
- 小学校・中学校・高校ごとの不登校の要因と対応方法
- 不登校の子どもの選択肢
- 不登校の子どもをもつ親ができること
不登校の生徒でも安心して通い、卒業できるのが通信制高校です。
通信制高校について詳しく知りたい方はこちら「通信制高校とは」を参考にしてみてください。
小学生・中学生・高校生の不登校の現状
文部科学省が発表した「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、不登校の現状は以下の通りでした。
小学校の学年別不登校児童生徒数
- 1年生…2,296人
- 2年生…3,625人
- 3年生…5,496人
- 4年生…8,089人
- 5年生…11,274人
- 6年生…14,061人
- 合計…44,841人
中学校の学年別不登校児童生徒数
- 1年生…31,046人
- 2年生…43,428人
- 3年生…45,213人
- 合計…119,687人
小学校と中学校では、不登校児童生徒数が年々増加していることが分かります。
高校の学年別不登校児童生徒数
- 1年生…13,481人(1.4%)
- 2年生…12,400人(1.3%)
- 3年生…9,082人(1.0%)
- 4年生…447人(8.5%)
- 単位制…17,313人(4.2%)
- 合計…52,723人(1.6%)
不登校生徒のうち中途退学・原級留置になった生徒の割合(高校)
- 途中退学…25.4%
- 原級留置…6.9%
高校は義務教育ではないため、不登校になった生徒が退学をするケースが多いです。
そのため、小学校・中学校と異なり学年が上がるごとに不登校者数が減少していることが分かります。
指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合
- 小学校…26.8%
- 中学校…26.4%
- 高校…29.5%
不登校になった生徒のうち、教師やカウンセラーによる指導により登校するようになったのは全体の2~3割です。
一度不登校になると、登校するようになるのは難しいといえます。
不登校の状態が前年度から継続している児童生徒の割合
- 小学校…42.6%
- 中学校…54.3%
- 高校…33.9%
こちらの結果からも、一度不登校になるとなかなか登校することができないことが分かります。
では、小学生・中学生・高校生はそれぞれどのような要因で不登校になるのでしょうか。
小学生が不登校になる要因
小学生が不登校になる要因を見てみると「家庭に係る状況」が55.5%で1位、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が21.7%で2位、「学業の不振」が15.2%で3位でした。
不登校というと真っ先に学校での人間関係を疑いますが、意外にも家庭などの学校外の要因で不登校になる人が多いのです。
また、学業の不振など、人間関係意外の要因で学校に行かない/行けない子どもも多いということが分かりました。
小学生の不登校の要因
- いじめ…0.8%
- いじめを除く友人関係をめぐる問題…21.7%
- 教職員との関係をめぐる問題…4.5%
- 学業の不振…15.2%
- 進路に係る不安…1.1%
- クラブ活動、部活動等への不適応…0.2%
- 学校のきまり等をめぐる問題…2.6%
- 入学、転編入学進級時の不適応…4.5%
- 家庭に係る状況…55.5%
- 上記に該当なし…13.7%
(文部科学省「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より)
小学校低学年は大人からすれば些細な環境の変化が原因で不登校になる可能性があります。
また、学年が上がると思春期に突入し、家族や先生、友人などを対象に人間関係の悩みを抱えることが増えるのです。
では、不登校の小学生にはどのように対応すれば良いのでしょうか。
不登校の小学生への対応方法
小学生の不登校に対しては、無理やり学校に行かせようとするのではなく、安心して学校に通えるまで時間をかけて寄り添いましょう。
不登校に対して罪悪感を抱える子どもも多いため「無理して学校に行かなくても良い」と伝えてあげることが大切です。
また、好きなことや得意なことをやらせてあげることで子どもが前向きになれるようにサポートしましょう。
中学生が不登校になる要因
中学生が不登校になる要因を見てみると「家庭に係る状況」が小学生と同じく1位(30.9%)、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が30.1%で2位、「学業の不振」が24.0%で3位でした。
順位は小学生と同じでしたが、友人関係をめぐる問題と学業の不振の割合が増えていることが分かります。
そこから、学年が上がるごとに学校での人間関係に悩む人が増えていると予想できますよね。
中学生の時点で毎日通学することが難しかったり、学業の不振に悩んだりする人の中には、高校進学が心配という人も多いようです。
中学生の不登校の要因
- いじめ…0.6%
- いじめを除く友人関係をめぐる問題…30.1%
- 教職員との関係をめぐる問題…2.5%
- 学業の不振…24.0%
- 進路に係る不安…5.3%
- クラブ活動、部活動等への不適応…2.7%
- 学校のきまり等をめぐる問題…3.4%
- 入学、転編入学進級時の不適応…7.7%
- 家庭に係る状況…30.9%
- 上記に該当なし…13.4%
(文部科学省「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より)
中学生も、急な環境変化がストレスとなり不登校になることが多いです。
そのため、入学後すぐや夏休み明けなどのタイミングで学校に行きたくなくなる/行けなくなることも。
また、高校進学やその先の進路について考える機会が増え、学力などを意識する時期でもあります。
インターネットに依存する人もいるなど、自分や現実と向き合い疲れてしまう子どももいるのです。
では、不登校の中学生にはどのように対応すれば良いのでしょうか。
不登校の中学生への対応方法中学生への対応は、小学生と同じく無理に学校に行かせようとしないことです。
その上で子どもが自分自身で考えて解決できるようなサポートが望ましいといえます。
「~しなさい」「どうして~できないの」と子どもを責めるのではなく「学校には行きたくなったら行けばいい」と優しく寄り添ってあげましょう。
高校生が不登校になる要因
高校生が不登校になる要因を見てみると、「学業の不振」が17.9%で1位、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が17.5%で2位、「家庭に係る状況」が15.3%で3位でした。
高校生が不登校になる要因は、小学生と中学生とは違うということが分かりますよね。
家庭に係る状況で不登校になる人の割合が大きく減り、学業や友人関係など直接学校に関わることで悩む子どもが増えるようです。
高校生の不登校の要因
- いじめ…0.4%
- いじめを除く友人関係をめぐる問題…17.5%
- 教職員との関係をめぐる問題…1.2%
- 学業の不振…17.9%
- 進路に係る不安…8.9%
- クラブ活動、部活動等への不適応…1.7%
- 学校のきまり等をめぐる問題…4.1%
- 入学、転編入学進級時の不適応…13.6%
- 家庭に係る状況…15.3%
- 上記に該当なし…29.0%
(文部科学省「平成 30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より)
高校生が不登校になる要因には、現実と理想のギャップに耐えられないというパターンもあります。
また、精神的に未熟な子どもが不登校になるというわけではなく、成熟しているために「勉強するよりも~したい」「学校に行く理由が分からない」と考える子どももいるのです。
では、不登校の高校生にはどのように対応すれば良いのでしょうか。
不登校の高校生への対応方法
不登校の高校生へは、休みたいという気持ちを尊重した上で興味のあることややりたいことをやることを応援する気持ちを示すことが大切です。
高校生は人間関係が上手くいかない、周りよりも勉強ができないなどという理由で落ち込んだり、将来に対して不安を抱いていたりします。
アルバイトや通信制高校への転入、就職などの選択肢があり、それらが決して受験よりも下ではないことを伝えてあげましょう。
現在、不登校で転入をご検討されている方は「通信制高校への転入を考えている高校生の方へ」 に詳しく転入について書かれているので、参考にしてみましょう。
不登校の小学生と中学生と高校生の違いは学校に要因があるかどうか
学年が上がるにつれ、学校に行くかどうかを自分の意志で決められるようになります。
高校は義務教育ではないため、学校に行きたくなければ辞めるという選択もできるようになりますよね。
しかし、小学生や中学生は簡単に転校することができないため、周りの大人が根気よく寄り添うことが大切です。
では、子どもが不登校になった場合、どこに相談すれば良いのでしょうか?
子どもが不登校になったらどこに相談すれば良い?
子どもが不登校になった場合、または子ども自身が相談する相手を求めている場合、以下の相談先が考えられます。
- 学校
- 不登校やいじめについて相談できる公的窓口
担任の先生やスクールカウンセラーに相談する以外にも、公的窓口に相談するという手があります。
また、不登校の生徒の対応に慣れている通信制高校に相談することで子どもにとって新たな選択肢を与えることも可能です。
家庭だけで抱え込まず、不登校の専門家に助けを求めることも大切だといえます。
不登校になった子どもには通信制高校という選択肢がある
不登校になった子どもには、通信制という選択肢があります。
中学卒業後にそのまま通信制高校に進学したり、全日制高校から転入したりすることで悩みが解決するかもしれません。
通信制高校の特徴やメリット
不登校の子どもにとって通信制高校のメリットは以下の通りです。
- 受け入れ体制が整っている
- 不登校への対応に慣れている
- 登校日や学習方法が選べる
- 同じ悩みを抱える生徒が通っている
通信制高校には同じ悩みを抱えている生徒がいます。
学校側も生徒に合った登校スタイルや学習方法、進路を提案してくれるため、全日制高校に通うよりも自由度が高いといえるでしょう。
不登校で悩んでいる子どもに是非通信制という選択肢を伝えてみてください。
不登校への対応に力を入れている通信制高校
- 中央高等学院
- トライ式高等学院
以上の通信制高校は不登校を積極的に受け入れています。
学校の先生に相談することで解決することもありますので、一度見学や資料請求を行ってみてはいかがでしょうか。
通信制高校のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は「通信制高校のメリットデメリットを完全解説」を参考にしてみましょう。
不登校で悩む子どもに親ができること
いかがでしたか?
不登校で悩む子どもをもつ親は、学校に行くことを強制したり怒ったりせず、子どもの気持ちを尊重し寄り添ってあげましょう。