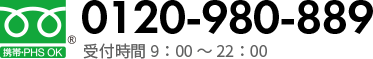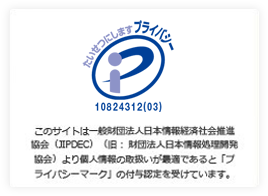高校学費無償化を徹底解説!年収別の支給額 更新時間 2026.01.08
高校進学を考える多くの家庭にとって、学費の負担は大きな課題です。
しかし、近年導入された高校学費無償化制度により、経済的なハードルが大きく下がりました。
この記事では、この学費無償化制度とよばれている「高等学校等就学支援金制度」について詳しく解説します。
さらに、世帯年収別の支給額や申請方法、必要書類についても紹介していきます。
これから高校進学を控えるご家庭にとって、有益な情報を提供できれば幸いです。
高校無償化制度とは?
高校無償化制度は、国の支援制度の一環であり、正式名称は「高等学校等就学支援金制度(以下、就学支援金)」と呼ばれています。
この制度は、日本国内に居住するあらゆる高等学校や高等専門学校などの対象校に在籍する一部の生徒に対し、返済不要で補助金を支給するものです。
ちなみに、国立・公立・私立は問いません。
2020年4月からは、私立高等学校等に通う生徒への支援金額が引き上げられ、多くの家庭で教育費の負担が軽減されるようになりました。
就学支援金制度の対象校
以下の学校に在学する方が対象となります。
- 高等学校(全日制、定時制、通信制)
- 中等教育学校(後期課程)
- 特別支援学校(高等部)
- 高等専門学校(1~3学年)
- 専修学校(高等課程)
- 専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
- 各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
支給金額と対象外条件
対象となる学校種類ごとに、支給される就学支援金額は異なります。
ただし、以下の条件に当てはまる場合は支給の対象外です。
- 高校等を既に卒業または修了した者や、在学期間が3年(定時制・通信制は4年)を超えた者
- 専攻科や別科の生徒、科目履修生、聴講生
- 一定の収入基準を超える世帯(モデル世帯で世帯年収合算目安910万円以上)の学生
制度の対象者になるためには、保護者の所得要件を満たす必要があります。
さらに、世帯年収についての具体的な枠組みはケースバイケースで決まりますので、受給の可否は学校への相談が必要です。
例えば、親が離婚している場合、世帯年収は主に生計を共にしており、養育をしている親の収入が基準になります。
同様に、祖父母と同居している場合は、主たる養育者である父や母の収入が世帯年収として考えられます。
また、入学者が20歳以上の場合には、自分の生計を維持している人の年収か、自分の収入のみが世帯年収とみなされることがあります。
これらは一般的なケースですが、個々の家庭状況によって異なる場合がありますので、具体的な受給条件については学校や関係機関に相談してみましょう。
また、万が一学費が払えなくなってしまった場合は「高校の学費が払えない時の対処法!学費を安く高校を卒業するには?」 で詳しく説明しているので参考にしてみてください!
【世帯年収別】就学支援金の支給額と条件
就学支援金は、世帯年収に応じて支給額が変わります。
公立高校と私立高校で支給額や条件が異なるため、それぞれの詳細について説明します。
公立高校の場合の支給額
公立高校では、世帯年収が910万円未満の場合、年間11万8800円が支給されます。
公立高校の授業料は年間約11万8800円以下であるため、世帯年収が910万円以下の家庭は授業料が実質0円になります。
ただし、年収910万円以上の家庭は支給対象外となるため注意が必要です。
私立高校の場合の支給額
私立高校では、世帯年収が590万円未満の場合、年間最大39万6000円の就学支援金が支給されます。
また、年収590万円から910万円の家庭には、公立高校と同等の年間11万8800円が支給されます。
ここでも、年収910万円以上の家庭は支給対象外です。
私立高校の授業料は高額なため、支援金で賄えない場合は実質自己負担となります。
世帯年収ごとの支給額の目安
支給額については、家族構成や労働状況によって変動します。
以下の表をよく確認し、どこに該当するかを把握しておきましょう。
(参考)支援の対象になる世帯の年収目安
| 子の人数 | 11万8,800円支給 | 39万6,000円支給 | |
|---|---|---|---|
| 片親のみ働いている場合 | 子2人(高校生・高校生) | ||
| 扶養控除対象者が2人の場合 | ~約950万円 | ~約640万円 | |
| 子2人(大学生・高校生) | |||
| 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 | ~約960万円 | ~約650万円 | |
| 両親共働きの場合 | 子2人(高校生・中学生以下) | ||
| 扶養控除対象者が1人の場合 | ~約1,030万円 | ~約660万円 | |
| 子2人(高校生・高校生) | |||
| 扶養控除対象者が2人の場合 | ~約1,070万円 | ~約720万円 | |
| 子2人(大学生・高校生) | |||
| 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 | ~約1,090万円 | ~約740万円 |
参考:文部科学省「私立高校授業料実質無料化リーフレット」
学費無償化の申請方法と必要書類
次に、支援金の申請方法について解説します。
就学支援金の支給方法
就学支援金は、生徒や保護者が直接受け取るのではなく、学校が代わりに受け取り授業料に充てます。
ただし、学校によっては支給決定までの間に授業料を一時的に徴収し、後日、支援金相当額を返金する場合があります。
経済的に困難な家庭には、授業料の支払いを猶予する措置が利用できることもあります。詳細については学校に問い合わせてください。
申請手続き
新入生の方の申請就学支援金を利用するには、申請が必要です。
入学時の4月などに学校から案内があるので、指示に従って手続きを行ってください。
申請が遅れると支給開始も遅れるため、注意が必要です。
都道府県による審査が終了次第、結果が通知されます。
在校生の方の収入状況の届出毎年7月頃、世帯の所得情報(課税額)が更新されるため、学校からの案内に従って収入状況を届け出る必要があります。
手続きを行わないと、7月以降の支援金が支給されないので注意してください。
なお、過去にマイナンバーを提出している場合など、一部の手続きが不要になることがあります。
都道府県による審査が終了次第、結果が通知されます。
申請に必要な書類
高等学校等就学支援金を受け取るためには、住民税所得割額を確認できる書類(住民税税額決定通知書、納税通知書、課税証明書等)やマイナンバーカードの写しなどを、認定申請書とともに学校経由で提出する必要があります。
課税証明書などで所得要件の確認を行い、支援金の受け取りが認定された場合、基本的に7月頃に必要書類を学校に提出する必要があります。
申請期限は学校によって異なるため、必ず期限を確認し、期限内に提出しましょう。
ただし、マイナンバーで所得要件を確認し、受け取りが認定された場合は、追加の書類提出は不要です。
課税証明書等で所得要件を確認する場合
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます)
- 市町村民税所得割額・道府県民税所得割額を確認できる書類(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
マイナンバー(個人番号)で所得要件を確認する場合
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます)
- マイナンバーカードの写し等(マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
東京都の高校授業料無償化について
2023年12月、東京都の小池百合子都知事は、都内のすべての高校の授業料を実質無償化する方針を発表しました。
これにより、2024年度から所得制限が撤廃され、多くの学生が授業料の負担から解放されることになります。
本章では、国の就学支援金との違いなどについて、詳しく解説します。
すべての世帯で私立高校授業料は実質無償
2020年4月から、全国の私立高校では授業料の無償化が始まっていますが、世帯収入に上限が設けられています。
一方、東京都では2024年度から都内の全ての高校で、授業料を実質的に無償化することを打ち出しました。
この施策は、2024年4月から実施されています。
具体的な支給額について見てみましょう。
| 世帯年収の目安 | 国の就学支援金 | 都の授業料軽減助成金 |
|---|---|---|
| 590万円未満 | 396,000円 | +88,000円 |
| 590万円〜910万円 | 118,800円 | +365,200円 |
| 910万円〜 | 0円 | +484,000円 |
東京都では、国の支援金に独自の補助金を上乗せし、年間最大48万4,000円まで引き上げられます。
また、年収が910万円以上の世帯についても、支給額を48万4,000円まで引き上げています。
年収目安は、保護者1人にのみ給与収入がある4人世帯(夫と子2人)及び、保護者2人に給与収入がある5人世帯(夫婦と子3人)をモデルとしたケースです。
支給額については、区市町村民税課税標準額等に基づき計算されます。
高校3年間の費用はどのくらい必要?
文部科学省の「令和3年度 子供の学習費調査」によると、全日制の公立高校の年間平均学習費は51万2,971円です。
この額には、入学料や授業料、その他の費用も含まれています。
私立高校の場合、年間平均学習費は105万4,444円となっています。
この調査から、公立高校の場合、授業料11万8,800円を差し引いた残りの39万4,171円が必要です。
私立高校では、支給される47万5,000円を差し引くと、57万9,444円が必要となり、私立の方が費用が高いことが分かります。
しかし、高収入世帯でも、学費全体の約45%が補助されるため、負担が軽減されることになります。
高校授業料が無料であれば私立高校が狙い目?
都内高校の授業料無償化の年収制限が撤廃されたことにより、「進学するなら私立の方がお得では?」と考える人もいるでしょう。
しかし、実際に無償化されるのは授業料だけです。
その他の入学費用や教科書代、学校納付金などは自費での負担となります。
調査でも、実費負担は私立高校の方が高くなることが示されています。
「お得かどうか」は親の視点に過ぎないかもしれません。
重要なのは、子どもが学びたい高校に進学し、自分らしい生き方を見つけることです。
学校の区分に関係なく、子どもの将来にとって意義のある選択をすることが大切です。
また、私立の通信制高校の学費が高いという方の声を「通信制高校の学費は高い!みんなの意見をまとめてみました!」 で詳しく説明しているので参考にしてみてください!
就学支援金の対象にならない費用
就学支援金は授業料の負担を軽減するための制度ですが、授業料以外の費用には適用されません。
ここでは、具体的にどのような費用が対象外になるのか、また足りない場合の対策について説明します。
就学支援金の対象は授業料のみ
就学支援金は、高校の授業料に対してのみ支給される補助金です。
そのため、教材費や制服代、修学旅行の費用など、授業料以外の経費には使用できません。
授業料以外の費用も含めて、教育費を計画する必要があります。
対象外の費用項目
就学支援金の対象外となる費用には、教材費、制服代、クラブ活動費、修学旅行費用、交通費などがあります。
これらの費用は、各家庭が別途準備する必要があります。
また、自治体によっては、これらの費用に対する独自の支援制度がある場合もありますので、確認しておくと良いでしょう。
就学支援金だけでは足りない場合は
就学支援金だけでは、全ての教育費を賄うことは難しい場合があります。
そのような場合には、奨学金の活用や自治体の補助金制度を検討することが重要です。
また、「家計急変支援制度」や「母子父子寡婦福祉資金」、国の教育ローンなども活用しましょう。
必要な支援を受けることで、教育費の負担を軽減することができます。
就学支援金の受給ボーダーの人ができる工夫
就学支援金には、世帯年収が910万円(共働きの場合は1,000万円程度)という受給のボーダーがあります。
この境界線ギリギリにいる場合、所得判定額を減らす方法を検討することが重要です。
以下に、具体的な方法を紹介します。
所得判定額を減らす方法
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で投資運用を行いながら資産を形成する年金制度です。
掛金は所得控除の対象となり、所得判定額を減らすことができます。
その他の控除
生命保険料控除や地震保険料控除など、税額決定通知書の所得控除欄に記載される項目も所得判定額を減らすことができます。
減額対象外の方法
ふるさと納税
ふるさと納税は、自治体に寄付をして返礼品を受け取る制度です。
2020年以前は所得判定額を減らすのに有効でしたが、現在は対象外となっています。
住宅ローン控除
マイホーム購入時に利用できる住宅ローン控除も、所得税から控除される制度ですが、就学支援金の所得判定額の減額対象にはなりません。
高校学費無償化の重要ポイントまとめ
今回は、高校学費無償化について詳しく説明しました。
無償化の対象は授業料のみであり、その他の費用は自費負担となります。
世帯年収に応じた支給額や申請方法、必要書類などを確認し、申請漏れがないよう注意しましょう。
また、2024年からの都内高校授業料無償化によって、私立高校への進学がより現実的になった点にも触れました。
親の視点だけでなく、子どもが自分らしく成長できる学校を選ぶことが重要です。
学費無償化の制度を活用し、子どもの未来を支えましょう。
また、学費が安いおすすめの通信制高校を「【おすすめ】学費が安い通信制高校をご紹介!」 で詳しく説明しているので参考にしてみてください!