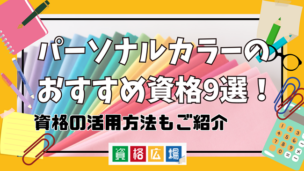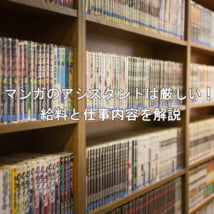陶芸家とは、日常的に使用される食器や花瓶、芸術作品のオブジェなどを作り出す職人のことです。
特別な免許や資格は必要ありませんが、生計を立てられる陶芸家になるには、どのような進路を歩めばよいのでしょうか。
このページでは、陶芸家になるにはどうしたら良いのか?作品の種類や収入、年収などについて解説しています。
陶芸家になるには、特に資格は必要ありません。ただし特別な知識や技術が必要です。
陶芸家とは

「陶芸家」とは、いわゆる「焼き物」を作り出す職業に就く人のことを指します。
私たちが日常的に使用している食器、花瓶、タイルはもちろん、オブジェなどの芸術作品もそれに含まれます。
特別な資格や免許は必要ありませんが、デザインや土に関する専門的な知識が求められるために、陶芸家一本で生計を立てられるようになるには難しい道のりを歩まなければなりません。
ただし、自分が生み出した作品が世間に評価されたり、喜ばれたりするほどの成果を出せるような陶芸家になれば、ものづくりが好きな人にとって大変なやりがいを感じられるでしょう。
陶芸家になりたい人の進路
陶芸家になるには資格や学歴は特に必要ありません。ただし特別な専門知識を学ぶ必要があります。
それを考慮すると、陶芸家になるには大きく分けて4つのパターンがあります。
1.学校へ通う
美大や専門学校などの陶芸コースへ通えば、いわゆる陶芸教室よりも専門的なことを教えてもらえる場合が多く、学校によっては著名な先生から直接指導を受けられます。
学校によっては製陶会社のインターンシップ制度や海外への派遣制度もあるので、実践的な工程を学べたり、芸術家としてのグローバルな視野を磨いたりできるでしょう。
先生やクラスメイトから合評(作品講評会)を受けられるのもメリットです。
通信大学で学ぶ
社会人の場合は、通信大学で陶芸について学ぶのもひとつの手です。短大や専門卒の人は2年で卒業できるコースもあります。
通信大学と聞くと「本格的に学べないのでは?」という疑問を持たれるかもしれませんが、基礎から表現までしっかり学習できる学校も存在します。
例えば、テキストや動画を参考に自宅で課題を制作し大学へ送れば、それを添削した後焼成して返却してくれるなど、家に窯が無くても実践的に学ぶことができるのです。
自宅学習と週末スクリーニングで実践的に学べる通信芸術大学もいくつかありますので、調べて検討すると良いでしょう。
職業訓練校へ通う
行政機関を通して通える職業訓練校にも、陶磁器科が開設されているところがあります。
卒業後はその行政機関のある県や市町村で就職するのが望ましいですが、基本的に授業料がかからないのが魅力です。
作業服や消耗品は自己負担となるところが多いので、その点は注意しましょう。
2.弟子入りする
著名な陶芸家や日本各所にある窯元へ弟子入りするのも、陶芸家になるための方法のひとつです。
大学や専門学校で学んだ後に弟子入りするパターンが多いようですが、何の知識も無い状態でもツテを辿ってお手伝いとして弟子入りする方もいます。
ただし、その場合は無給または薄給であることを覚悟しておくべきでしょう。
いわゆる下積み時代は、オリジナル作品の制作やろくろに触ることも許されないというような厳しい環境が待ち受けているかもしれません。
しかしその分、自分の作品を作るのが許される頃には一通りの技術が身についているはずです。
最近ではインターネットで弟子やインターンを募集している場合もありますので、まずはWebページをチェックしてみると良いでしょう。
数年勤めれば「陶芸家○○に師事」と自身の経歴として公にして良い、とするところもあります。
独立までの道のり
十分な知識と技術が身についたら独立しよう!と思う方は多いはずです。
陶芸家として収入を得て独立するまでの道のりの一例をご紹介します。
独立場所を探す
まず、窯を構えるための場所(工房をつくる場所)を探す必要があります。
元々土地を所有している人は、その場所を活用する人が多いようです。
また、窯をつくる場所とは別に原材料(土や釉薬など)の保管場所、作業スペースも必要ですので注意しましょう。
制作部屋を準備する
ろくろや窯など制作に必要なものを準備します。
ろくろはおよそ10万円前後、窯は電気釜かガス窯ならば100万円前後で購入できるようです。
窯は消防署の検査が必要な場合があるので注意が必要です。
その他、材料を入れる棚や、自分の作品を自分で販売するのならギャラリースペースも用意したほうが良いでしょう。
新品ではなく中古品で揃えることで、初期費用はかなり低く抑えられます。
ちなみに、伝統工芸の窯元では若い作家向けにスペースを貸し出しているところもあるので、そのような情報も積極的に集めると良いでしょう。
取引先を見つける
制作部屋の準備と同時に、土や薬を仕入れる業者を見つけておくのも必要です。もちろん、自分自身で土を精製するのであればそれでも良いでしょう。
しかしすべての原料を自分で一から作らないのであれば、良い陶土を安定して供給してくれる業者を早い段階で見つけておいたほうが良いでしょう。
釉薬の主原料が堀り尽くされて市場から消えてしまった……、ということも珍しくありません。
安定して原料を手に入れられるようになるには、常に新しい情報をもらえるように取引先と良好な関係を築いておくのも大切です。
どのようなところで働くか

陶芸家になるために学んだ人すべてが独立し、自分の窯元を持ち、作家活動だけで生計を立てるわけではありません。
具体的にはどのようなところで働くのでしょうか。
・窯元や工房に所属し、同じものを大量につくる職人となる。
・アーティストとして活動し、自分の作品を個展などで販売する。
・陶芸教室を開き、先生として活動する。
作家活動とこれらの活動を合わせて生計を立てている陶芸家が多いようです。
年収は、修行期間を終えた段階でおよそ数十万円~300万円前後と言われます。
自分の知名度が上がるにつれて年収も上がる傾向にあるので、一流の陶芸家になるには様々な陶芸公募展に応募しながら生計を立てていくと良いでしょう。
陶芸家になるにはどうしたら良いのか?のまとめ
陶芸家になるにはどのような進路へ進めば良いのか?年収や収入の情報についてまとめました。
「土練り三年、ろくろ八年」と言う言葉があるように、陶芸は実力主義の世界です。
知識と技術を生涯に渡り学ばなければならない世界ではありますが、自分の作品が世間に認められた時の喜びは何ものにも代え難いものとなるでしょう。