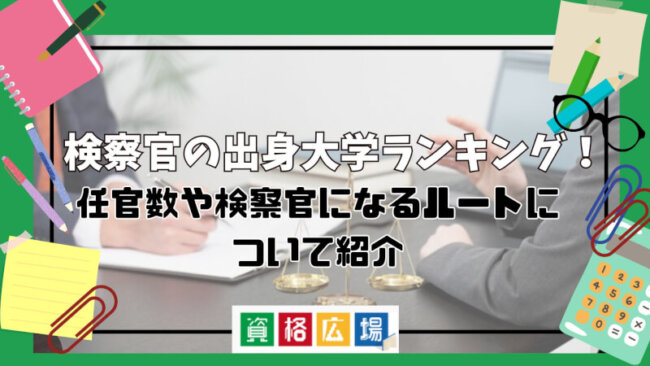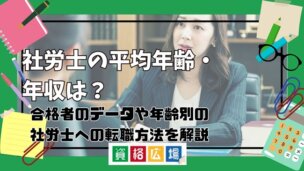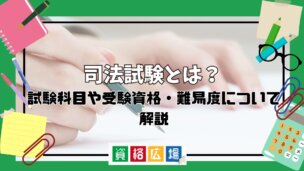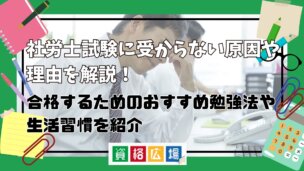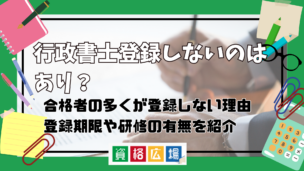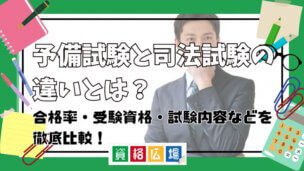検察官は犯罪の捜査や刑事裁判を行う国家公務員であり、被疑者の取調べや被害者からの聴取、証拠品の収集や精査などを行う仕事です。
検察官は法曹三者と呼ばれる「弁護士」「裁判官」「検察官」の職業の1つですが、検察官を目指すのは難易度が高いと言われています。
検察官になるためには難関国家資格である司法試験に合格しなければいけません。
そこで今回は検察官の出身大学や法科大学院、検察官のなり方などについて紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
検察官になるためのルート
先にも述べたように、検察官になるためには司法試験に合格しなければいけません。
司法試験は誰でも受験できるわけではなく、以下のうちいずれかのルートで進む必要があります。
ここでは、それぞれのルートの特徴について紹介します。
| 受験資格 |
|
|---|---|
| 回数制限 |
いずれも5年間の受験期間の中で5回まで受験可能。 |
| 試験内容 | 短答式と論文式による筆記。 短答式:憲法、民法、刑法 論文式:
※選択科目:知的財産法、労働法、租税法、倒産法、経済法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)、環境法 |
| 受験費用 | 28,000円 |
| 試験日 | 例年7月中旬の4日間 |
法科大学院ルート
法科大学院の課程を修了することで、司法試験の受験資格を得ることができます。
法科既修者コースの場合は2年、法科未修者コースの場合は3年の期間が必要です。
予備試験と比較すると時間や学費などの長期的な負担がありますが、司法試験の受験資格を得るためには確実なルートといえます。
法科大学院のルートでは課程を修了した日以降の4月1日から5年間が受験資格の有効期限となります。
各法科大学院によってその特徴や難易度が違うため、特に検察官志望の場合には検察官をたくさん輩出している大学院に進学するのがおすすめです。
合格者が多い大学院を選ぶことで質の高い講師からの指導を受けられるだけではなく、モチベーションの高い生徒同士で切磋琢磨できるメリットがあります。
予備試験ルート
司法試験は予備試験に合格することで最短で受験資格を得られます。
予備試験は毎年5月、7月、10月に実施され、3回に分かれて行われます。
すべての予備試験に合格すればのちに紹介する法科大学院生よりも早く司法試験に挑戦することができるので早く受験資格を得たい人におすすめです。
法科大学院生は、法科既修者コースで2年、法科未修者コースで3年の課程を修了しなければいけません。
ただし、予備試験では短答式試験、論文式試験、口述式試験の3つの試験を順に合格しなければならず、試験内容も広範囲にわたり、合格率も例年4%程度と司法試験よりも低いため狭き門です。
その分、予備試験ルートの方が司法試験の合格率が高く、就職でも有利になるメリットがあります。
また予備試験に合格した日から4月1日以降の5年間が司法試験の受験資格の有効期限となるため注意が必要です。
司法試験の合格率・難易度
| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 23.10% | 8,016人 | 1,850人 |
| 平成28年度 | 22.90% | 6,899人 | 1,583人 |
| 平成29年度 | 25.90% | 5,967人 | 1,543人 |
| 平成30年度 | 29.10% | 5,238人 | 1,525人 |
| 令和元年 | 33.60% | 4,466人 | 1,502人 |
| 令和2年 | 39.20% | 3,703人 | 1,450人 |
| 令和3年 | 41.50% | 3,424人 | 1,421人 |
| 令和4年 | 45.50% | 3,082人 | 1,403人 |
| 令和5年 | 45.3% | 3,928人 | 1,781人 |
| 令和6年 | 42.13% | 3,779人 | 1,592人 |
多少の変動はあるものの、近年の士補試験の合格率は40%程度で推移していることがわかります。
ちなみに、他の法律関連資格の合格率を見てみると、司法書士試験の合格率は3~5%程度、行政書士試験の合格率は8~15%程度、宅建の合格率は15%~18%程度となっています。
司法試験予備試験の合格率が毎年4%前後であることを考慮すると、司法試験の合格率は一見すると高いように思われます。
単に合格率だけを見ると司法試験はそれほど難しくないと誤解されるかもしれませんが、合格率だけで司法試験の難易度を判断するのは早計であると言えます。
司法試験予備試験の合格率
ここでは、司法試験予備試験の合格率について紹介します。
| 西暦 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 10,334人 | 394人 | 3.8% |
| 2016年 | 10,442人 | 405人 | 3.9% |
| 2017年 | 10,743人 | 444人 | 4.1% |
| 2018年 | 11,136人 | 433人 | 3.9% |
| 2019年 | 11,780人 | 476人 | 4.0% |
| 2020年 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |
| 2021年 | 11,171人 | 467人 | 4.0% |
| 2022年 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |
| 2023年 | 13,372人 | 479人 | 3.5% |
| 2024年 | 15,764人 | 461人 | 3.6% |
予備試験の合格率は4.0%前後で推移していました。
司法試験と違って受験者数は減少しておらず、毎年11,000人前後の多く方が受験されています。
しかし、2022年以降受験者数が増加しており、合格者数は例年とほぼ変わりないため合格率が4%を少し下回る結果です。
また、予備試験の合格者の司法試験の合格率は法科大学院の卒業生より高いというデータが出ています。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 予備試験合格者 | 475人 | 441人 | 約92%> |
| 法科大学院卒業生 | 2,072人 | 471人 | 約23% |
| 法科大学院在学中 | 1,232人 | 680人 | 約55% |
| 合計 | 3,779人 | 1,592人 | 約42% |
※出典:法務省「令和6年司法試験法科大学院等別合格者数等」
上記の表の通り、予備試験合格者の司法試験合格率は約92%と非常に高くなっています。
合格率4.0%前後の予備試験を合格した方は、その後本試験までしっかり勉強すれば、司法試験でも十分に合格できるレベルであるといえます。
予備試験合格者の受験者数は法科大学院の卒業生の数と比べると少ないですが、その圧倒的な合格率で司法試験全体の合格率を底上げしていることがわかります。
検察官の出身法科大学院ランキング
ここでは、検察官の出身法科大学院について紹介します。
法科大学院ルートの場合
第77期検事任官者数
67期(平成26年)~76期(令和5年)の検事任官者数をまとめると以下の通りとなります。
| 法科大学院名 | 合計 |
|---|---|
| 東京大学法科大学院 | 13 |
| 一橋大学法科大学院 | 12 |
| 慶應義塾大学法科大学院 | 11 |
| 早稲田大学法科大学院 | 11 |
| 京都大学法科大学院 | 7 |
| 北海道大学法科大学院 | 6 |
| 大阪大学法科大学院 | 3 |
| 中央大学法科大学院 | 3 |
| 東北大学法科大学院 | 2 |
| 名古屋大学法科大学院 | 2 |
| 岡山大学法科大学院 | 1 |
| 関西大学法科大学院 | 1 |
| 千葉大学法科大学院 | 1 |
| 同志社大学法科大学院 | 1 |
| 立命館大学法科大学院 | 1 |
第76期検事任官者数
66期(平成25年)~ 75期(令和4年12月)の検事任官者数をまとめると以下の通りとなります。
| 法科大学院名 | 合計 |
|---|---|
| 早稲田大学法科大学院 | 14 |
| 京都大学法科大学院 | 8 |
| 大阪大学法科大学院 | 6 |
| 東京大学法科大学院 | 6 |
| 一橋大学法科大学院 | 6 |
| 慶應義塾大学法科大学院 | 4 |
| 中央大学法科大学院 | 3 |
| 名古屋大学法科大学院 | 3 |
| 千葉大学法科大学院 | 2 |
| 東京都立大学法科大学院 | 2 |
| 東北大学法科大学院 | 2 |
| 法政大学法科大学院 | 2 |
| 愛知大学法科大学院 | 1 |
| 神戸大学法科大学院 | 1 |
| 上智大学法科大学院 | 1 |
| 専修大学法科大学院 | 1 |
| 創価大学法科大学院 | 1 |
| 筑波大学法科大学院 | 1 |
| 日本大学法科大学院 | 1 |
| 北海道大学法科大学院 | 1 |
| 立教大学法科大学院 | 1 |
| 立命館大学法科大学院 | 1 |
参照:第76期検事任官者(法科大学院・大学別任官者数)
司法試験の合格者は例年1400人〜1,500人程度で推移していることを考えると、検事に任官するのは70人程度であり、毎年5%程度となります。
以上のことから、検察官は弁護士よりも狭き門であるといえます。
予備試験ルートの場合
第77期検事任官者数
67期(平成26年)~76期(令和5年)の検事任官者数をまとめると以下の通りとなります。
| 法科大学院名 | 合計 |
|---|---|
| 一橋大学 | 2 |
| 京都大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 南山大学 | 1 |
第76期検事任官者数
| 法科大学院名 | 合計 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 神戸大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 一橋大学 | 1 |
参照:第76期検事任官者(法科大学院・大学別任官者数)
司法試験予備試験合格者は例年450人〜480人前後で推移していますが、76期・77期で予備試験ルートからの検事任官者数は7~8名で、予備試験の合格者の2~3%程度です。
以上のことからそもそも検事になる人自体が少ないといえます。
検察官になるには年齢は関係なし?ルートや必要な偏差値について解説
検察官とは
検察官とは検事や副検事を指し、公益の代表者として刑事事件に関して裁判所に公訴を提起する権限を有する国家公務員であり、法務省所属です。
検察官は裁判所に対して起訴し、その処罰を求める責任を負う仕事を行っています。
警察からの捜査記録を確認するだけでなく、被疑者の取調べや被害者・目撃者などの事件関係者から事情を聴取し、証拠品の捜索・差押え、さらにはその分析・検討を自ら積極的に行うことで事件の真相解明に努めています。
また、起訴後に被疑者が有罪であることを法廷で主張し、適正な刑罰の適用を求めることも検察官の重要な役割のひとつです。
検察官の働き方
検察官のおもな職場として最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁などが挙げられます。
ほかにも法務省での勤務や他の官庁への出向もあり、定期的に異動が行われます。
業務内容は被疑者の取調べや被害者等からの聴取、証拠の分析、法廷での活動などが中心であり、これらを検察事務官がサポートしています。
勤務時間は原則として1日7時間45分ですが、捜査や公判の状況に応じてそれを超えることもあります。
検察官は男性が約8割を占めていますが、女性の任官者が増得ている傾向にあり最近の検事採用実績では3割を超えています。
ちなみに検察官の定年は63歳であり、最高検察庁の長である検事総長の定年は65歳となっています。
司法試験突破を目指すならアガルート
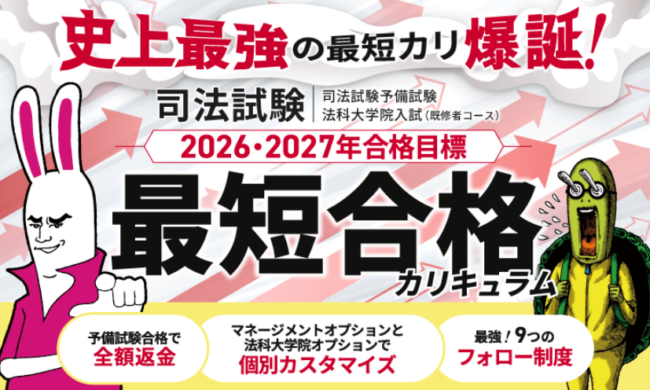
今回は検察官の出身大学や法科大学院、検察官のなり方などについて紹介してきました。
どの法科大学院、大学も検察官を育成する為の対策に力を入れています。
中でも以下の法科大学院・大学は検事の輩出が多い傾向にあることがわかりました。
- 京都大学法科大学院
- 慶應義塾大学法科大学院
- 東京大学法科大学院
- 中央大学
- 東京大学
- 早稲田大学
- 慶應義塾大学
司法試験を受けるには予備試験ルート・法科大学院ルートがあり、いずれにしても独学ではかなり難しいでしょう。
アガルートでは予備試験ルートや法科大学院ルートどちらにも対応しているのでおすすめです。
受講費用はやや高めに設定されている者の、キャンペーンや割引も多く実施されているのでお得に受講できます。